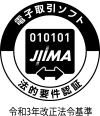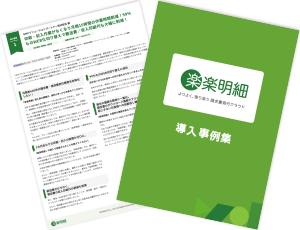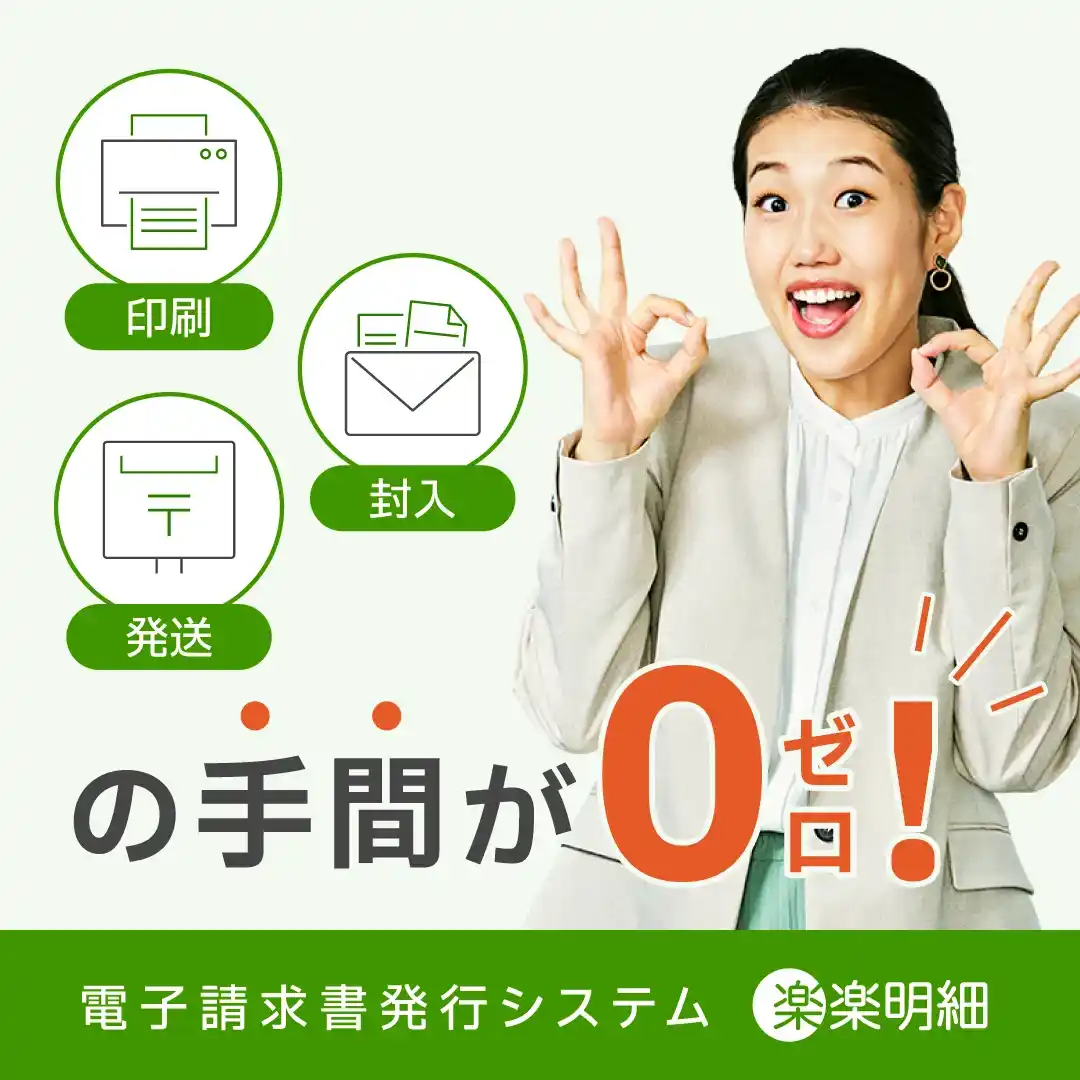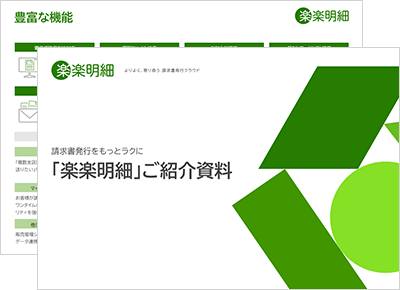請求書の電子化を拒否されたら?断られる主な理由や取引先への対処法

近年は電子帳簿保存法の整備などを背景に、多くの企業が請求業務のDXやペーパーレス化に取り組んでいます。そんな中、発行側の企業が請求書を電子化する際、受領側から「電子での受け取りはできない」と拒否されるケースがまれに見られるようです。
もしも取引先から電子化した請求書の受け取りを拒否されてしまったら、発行側の企業はどのように対処すればよいのでしょうか。この記事では、請求書の電子化を拒否される主な理由を深堀しながら、社内の電子化を推進する方法を考えていきます。
なお、請求書の電子化に伴うメリット・デメリットなどの基本的な知識については、以下の記事で詳しく解説しています。電子化を検討している経理担当者の方は、こちらもぜひご参考ください。
関連記事:「請求書の電子化とは?メリットやデメリット、導入のポイント」

そもそも請求書の電子化は拒否できる?
受領側の企業が請求書の電子化を拒否しても、法的には問題がありません。受領側の企業の状況や社内ルールによっては、請求書の電子化に対応できないケースもあり得ます。例えば、社内規則で請求書の原本を紙で扱うことが定められている企業では、自社のルールに準拠して運用しなければならないため、請求書の電子化に対応できない可能性があるでしょう。
そうはいっても、業務効率化を実現するために、取引先に電子化に応じてもらいたいと考えている発行側の担当者の方も多いのではないでしょうか。以降の見出しで請求書の電子化を拒否される理由を確認した上で、対処法を考えましょう。
請求書の電子化を拒否される理由
そもそも、なぜ取引先は請求書の電子化を躊躇してしまうのでしょうか。ここでは、請求書の電子化を拒否されてしまうときに考えられる理由を、受領側の企業の目線に立ってお伝えします。
業務フローを変えたくないから
「すでに社内に定着している業務フローを変更すると多くの時間と手間が発生する」というデメリットが理由で、請求書の電子化を拒否するケースがあります。電子化にともない、既存の業務フローや承認フローが変わると、一時的に現場が混乱する可能性があるほか、場合によってはマニュアルや人員の配置を見直す必要性も出てくるでしょう。
特に、改正電子帳簿保存法で2022年1月1日から「電子取引のデータ保存」が義務化されたことを背景に、電子化を躊躇する受領側の企業が少なくありません。電子データで受領した帳票書類は、原則として紙に印刷して保存することができず、電子保存する必要があります。オペレーションを整備する負担を心配している担当者も多くいるでしょう。
出典:国税庁HP「電子帳簿等保存制度」
紙に印鑑を押す慣習が定着しているから
古くから事業を続けている企業では、現場の担当者が長年にわたり業務に携わってきた背景から、紙での運用が根強く定着しているケースが見られます。書面に押印された請求書を受領する商習慣を、唐突に変えることに強い抵抗を感じて、電子化を拒否されてしまう可能性があります。
セキュリティに不安を感じているから
企業によっては、「電子化でハッキングや情報漏えいのリスクが高まるのではないか」とセキュリティ対策の観点で不安を感じていることがあります。特に担当者のITリテラシーによっては、よくわからないシステムを業務に取り入れることになるため、余計に電子化に対する不安感が大きくなりやすいのが注意点です。

請求書の電子化を拒否された際の対処法
もしも取引先に請求書の電子化を拒否されてしまったら、一度両社で話し合いの場を設けて、電子化へ向けて少しでもフォローできることがないか確認してみましょう。
電子化のメリットを伝える
請求書を電子化すると、発行側の企業だけでなく、受領側の企業にも多くのメリットがあることを伝えましょう。その際は、経理業務にもたらされるメリットを具体的に伝えることがポイントです。例えば「郵送よりも早く請求書を受け取れるようになります」「過去の請求書を検索できるので、簡単に書類を探せます」といった伝え方をするとよいでしょう。メリットに関心を持ってもらうことで、電子化を承諾してもらえる可能性が高まります。
段階的な電子化の導入を提案してみる
一度に全ての業務フローを電子化しようとすると、導入のハードルが高まりやすいといえます。そのため、まずは一部の請求書のみを電子化するよう提案して、順を追って取り組めないか話し合うのも一つの手です。例えば、「初めに第一営業部宛ての請求書を電子化する」、そして「第一営業部の電子取引がスムーズにできるようになったら、第二営業部宛ての請求書を電子化する」といったように、スモールスタートで進めるとよいでしょう。
電子化のサポートを提案してみる
取引先のITリテラシーによっては、システムの操作やファイル管理などの作業に不安を感じている可能性があります。この場合、発行側が事前に取引の流れや電子請求書の管理方法を説明するなど、適切な支援をすることで担当者の不安を軽減できるかもしれません。必要に応じて、担当者が不安に感じている内容をヒアリングして整理し、課題を解決するサポートを提案してみましょう。
請求書の電子化を拒否されたらフォローを検討!
ここまで、取引先に請求書の電子化を拒否される理由や、請求書の電子化を拒否された際の対処法を解説しました。
既存の業務フローや商習慣を変えるのが難しいという理由から、電子化を躊躇する取引先もいるかもしれません。そんなときは、相手方と話し合いの場を設けて、電子化へ向けたフォローを検討するとよいでしょう。
「どうしても紙で対応しなければならない」という取引先がある場合は、電子・紙の両方に対応できるクラウド型電子請求書発行システム「楽楽明細」の利用がおすすめです。「楽楽明細」の魅力を以下にまとめました。
「楽楽明細」の魅力① 電子・紙どちらの発行形式にも対応できる
「楽楽明細」なら取引先ごとに請求書の発行方法を選択できます。システム上で「WEB発行」「メール添付」「郵送代行」「FAX」の送付方法から個別に選ぶことが可能です。取引先のリクエストに応じて、電子・紙どちらの発行形式にも柔軟に対応できます。
「楽楽明細」の魅力② 取引先も便利になる
「楽楽明細」は自社の取引先にも多くのメリットをもたらします。オンラインで請求書をやり取りすると、郵送よりも早く受領できるため、支払処理がスムーズになります。過去の請求書はいつでも確認・ダウンロードできるので、物理的な紛失リスクがなく、再発行依頼などのコミュニケーションもなくなるため、請求書管理の効率化が図れます。
「楽楽明細」の魅力③ わかりやすいデザインで操作が簡単!
「楽楽明細」のシステムはシンプルな画面設計で、直感的に操作できます。請求書発行業務に特化した機能で、デザインがわかりやすいので、現場での使いやすさも大きな魅力です。システムが得意ではない方でも安心してお使いいただけます。
「楽楽明細」の魅力④ サポート体制が充実
「楽楽明細」では、取引先に送るWEBへの移行案内文のテンプレートや、取引先向けのシステム利用マニュアルをご用意しています。10,000社以上の導入実績を誇り、導入サポート実績も豊富です。電子化を受け入れていただくためのサポート体制が充実しています。
「楽楽明細」の機能や詳しい料金は、以下の無料資料でご案内しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
【無料】3分でわかる!電子請求書発行システム「楽楽明細」資料請求はこちら>>>
「楽楽明細」
請求書の印刷・封入・発送の作業をゼロに!
面倒な請求書発行の手間を削減します。
オススメの人気記事
- 記事執筆者紹介
- 株式会社ラクス「楽楽明細」コラム編集部
「楽楽明細」のコラムでは請求書や領収書、支払明細書などの各種帳票の発行方法や、経理業務を効率化する方法などについてご紹介します!

注目記事
96%削減できます。※
※ 月の発行件数500件の場合の月間の導入効果(ラクス調べ)


「楽楽クラウド」サービスのご紹介
「楽楽クラウド」サービスのご紹介です。
企業のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ95,000社以上のご契約をいただいています(※2025年3月末現在)。「楽楽明細」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。