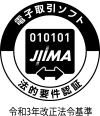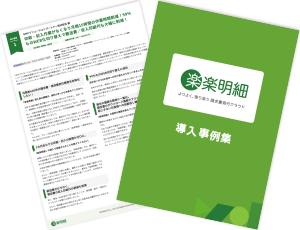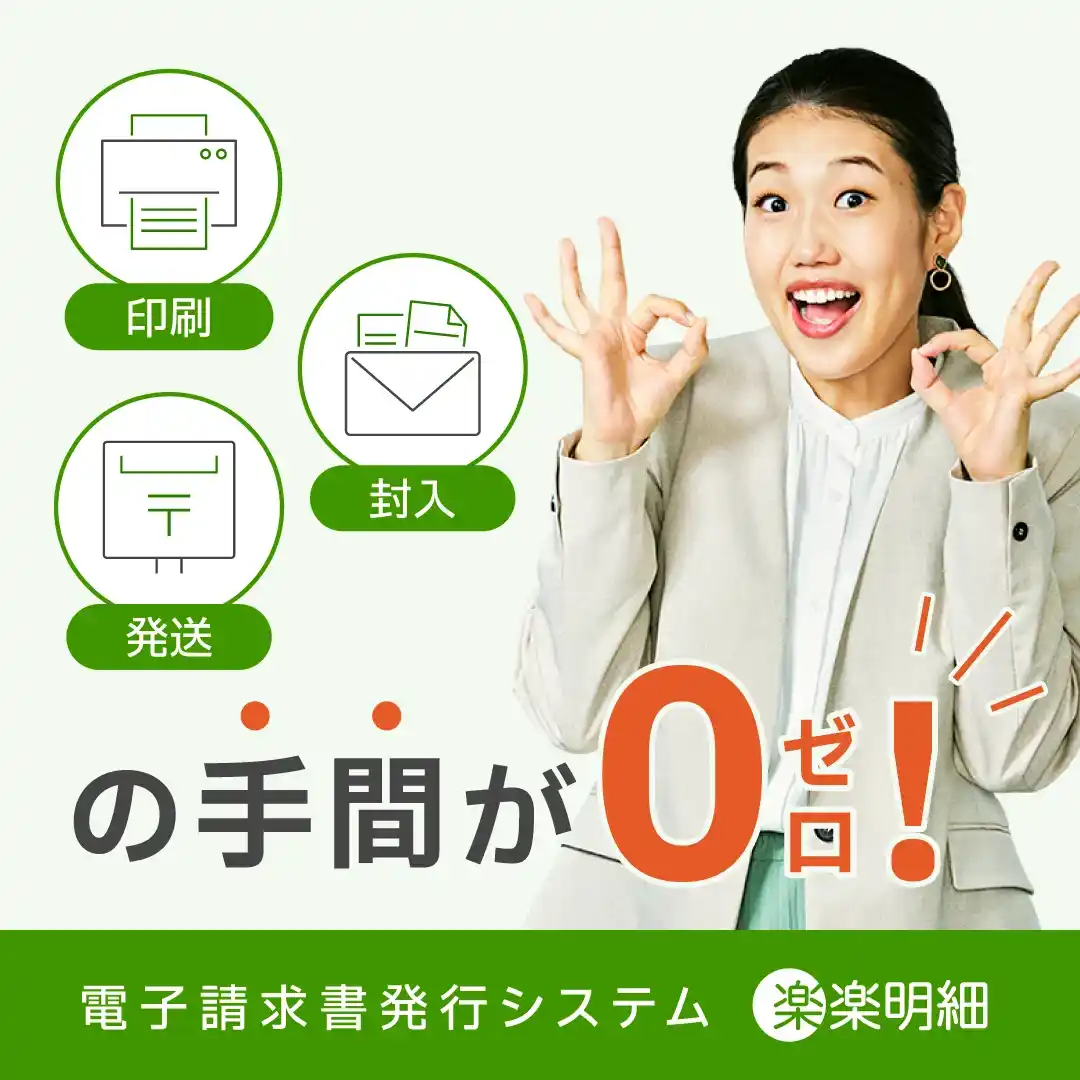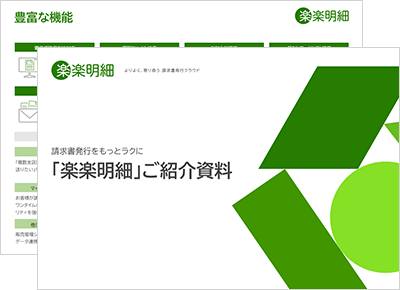請求書をメールで送る際のマナーや文例は?注意点を押さえて業務を楽に

取引先の企業に送る請求書は、普段どのように送付していますか?
近年は郵送ではなくメールで送付する会社も増えている一方、
「請求書をメールに添付して送る場合、法律や税制上の注意点はある?」
「紙で出力して送らないと、取引先に失礼にあたる…?」
といった懸念や疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、意外と知られていない請求書のメール送付に関するマナーやポイントについて解説します。送付時のメール文例も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
請求書の電子化について、網羅的に解説している記事はこちら>>>

この記事の目次
請求書はメールで送付しても大丈夫?
結論からお伝えすると、請求書はメールで送付できます。郵送で送付することが当たり前になっている会社で働いていると、メールでの送付に対して抵抗を感じるかもしれません。
支払いトラブルが起こった場合、論点となるのは請求行為が残っているかどうかです。送付方法にかかわらず、請求の意志表示があれば法律上有効です。そのため、メールで送付した請求書(電子請求書)は紙の請求書と同等の効力を有します。
近年テレワークの普及・電子帳簿保存法の法改正・ペーパーレス化の推進に伴い、メールでの請求書送付に切り替える企業が増えています。取引先から要望があり、メール送付をはじめるケースもあります。
請求書をメールで送付する際のマナー
請求書をメールで送付する際によくある疑問・不安を解消すべく、メール送付時のマナーについて解説します。
マナー1:取引先への事前確認
請求書の送付を郵送からメール送付に切り替える場合は、送付する取引先へ一報入れるのがマナーです。自社の請求管理がオンライン化することで、先方の事務処理に変更が生じる可能性に配慮し、事前に了承をもらうようにしましょう。
了承を得る際は、電子請求書の送付先や、CCに追加するべき担当者名・アドレスをあわせて確認してください。取引内容を関係者に漏れなく共有でき、スムーズなやり取りにつながります。
連絡手段としては、メールや電話が一番早い方法です。ほかに、今後メール送付に切り替える旨を記した案内文を、請求書を送るタイミングで一緒に郵送する方法があります。
案内文には、メール送付の切り替え時期と、問い合わせ窓口の担当者名・連絡先を明記しましょう。取引先の確認漏れを回避するために、承諾可否の返信用ハガキを同封するのもひとつの手です。承諾を得られなかった場合は、個別で郵送などの対応が必要になります。
マナー2:押印の必要性の確認
メール送付の可否とあわせて、電子請求書に押印が必須かどうか、取引先に確認しましょう。
印影がない請求書も法的効力を発揮するため、基本的に押印は不要です。ただし、取引先の会社のルールで、押印されていない請求書を受け付けないケースがあります。押印なしでも受領してもらえるかどうか、事前に取引先へ確認してください。
押印が必要な場合は、電子印鑑サービスを利用し、請求書データに電子印を押印します。電子印鑑サービスは無料で利用できる場合が多く、誰でも簡単に押印できます。
電子印鑑の法的効力や必要性は、以下の記事をチェックしてください。
関連記事:「請求書に電子印鑑は使用できるの?電子印鑑の作り方や法的効力についても徹底解説」
マナー3:件名の書き方
請求書をメールで送付する際は、重要なメールであるとわかる件名をつけましょう。
取引先担当者のメールボックスには、日々さまざまな内容のビジネスメール・ダイレクトメールが届きます。メールが埋もれてしまうと、取引先が請求書に関するメールを見落とし、支払期日までに入金してもらえない可能性があります。
毎月送るメールの件名を、下記の例文のような書き方で統一すると、検索性が上がり、先方がメールを見つけやすくなります。
<例>
○○株式会社_□年××月分請求書のご案内
マナー4:送付形式
請求書を送付する形式には、法令上厳密なルールがありません。ただし、データが改ざんできないよう、PDF形式で送付するのが一般的なマナーです。
WordやExcelで請求書を送付すると、操作ミスにより意図しない改ざんが起こりえます。ファイルにパスワードを設定し、編集できないようにしても、改ざんのリスクをゼロにすることはできません。また、パソコンの動作環境の違いで、ファイルが開けない懸念があります。
元データはWordやExcelといった作りやすい形式で作成し、送付するデータはPDF形式を用意してください。改ざん・変更できない形式で請求書を送付することは、自社と取引先の双方にメリットがあります。
なお、請求書をPDF化した場合の法的な有用性については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:「請求書をPDF化した場合の法的な有効性は?電子化のメリット・デメリットについても解説」
マナー5:ファイル名の付け方
メールの件名と同様に、請求書のファイル名は毎月同じ付け方に統一しましょう。
取引先の経理担当者は、各社から送付される膨大な請求書のデータを正確に保管しなければなりません。作成者や詳細がひと目でわからないファイルは、整理するときに取引先の手間をかけることになってしまいます。
ファイル名には、作成者(自社の社名)と請求年月を明記してください。ファイル同士の識別性を高めるために、ファイルごとに異なる請求番号を割り振って記載しましょう。
取引先名をファイル名に記載する場合は「(会社名)御中」と記載するのがマナーです。
<例>
【請求番号:--------】○○株式会社 御中|(自社名)□年××月分請求書
マナー6:原本の必要性の確認
請求書をメール送付する際は、別途原本(紙)の送付が必要か確認しましょう。法令上は不要でも、取引先のルールや請求業務の兼ね合いから、原本の提出を求められる場合があります。
電子請求書は月末までに提出し、原本(紙)は翌月10日までに送付するなど、提出期限が異なる可能性があります。事前に「何を」「いつまでに」送付すればいいか、取引先へ確認しましょう。
原本の送付が必要な場合は、送付した旨をメールや電話で取引先に知らせてください。請求メールの本文で「本日原本を貴社宛に送付いたしました」といった旨を伝えると、より丁寧な対応です。
電子請求書と原本を両方送付する場合は、送付する手間が倍になってしまうのが難点です。請求書の原本の送付を求められた場合は、メールではなく紙で郵送してしまうほうが効率的かもしれません。

メールで請求書を送る際の2つの文例
請求書をメールで送る際に重要なのが、件名と本文です。他のビジネスメールに埋もれないよう、件名のつけ方を工夫する必要があります。
メールは請求金額だけ提示した文面で送ると、失礼な印象を与えてしまいかねません。丁寧なメール文を作成することで、取引先との関係を良好に保てます。
下記の請求書送付時の文例を参考に、メールを作成してみましょう。
【文例1】初めて請求書を送る取引先にメールで送付する場合
初めて請求書をメールで送る場合は、丁寧な挨拶文を心がけましょう。件名・添付するファイル名・開封できなかった場合の対応をわかりやすくまとめると、担当者がスムーズに対応できます。
<例>
件名:○○年○○月_△△△に関するご請求書(①)
□□□□株式会社 □□部 御中(②)
平素より格別のお引き立てをいただき、御礼申し上げます。
▲▲▲▲社▲▲部の▲▲▲▲と申します。(③)
この度は、△△△のご依頼をいただきまして、
誠にありがとうございます。(④)
早速ではございますが、請求書をメールにて
送付させていただきます。
また、添付ファイルが開封できないなどのお困りの場合や
ご不明な点などございました際には、ご連絡いただけますよう
何卒よろしくお願いいたします。(⑤)
【添付内容】
・請求書No.19-001 ■■■.pdf 1通(⑥)
なお、誠に勝手ながら振込手数料はお客様にてご負担くださいますよう
何卒よろしくお願いいたします。(⑦)
▲▲▲▲社 ▲▲部
▲▲▲▲
住所 東京都▲▲区
TEL 03-▲▲▲-▲▲▲▲
FAX 03-▲▲▲-▲▲▲▲
E-MAIL ▲@■■.com
携帯 090-▲▲▲▲-▲▲▲▲(⑧)
文面のポイント
①件名
メールで請求書を送る場合は、ビジネスメール・ダイレクトメールと区別できるよう、ひと目見ただけで請求書だとわかる件名をつける必要があります。
正:件名 ○○年○○月_△△△に関するご請求書
誤:件名 株式会社○○御中
②宛名
一般的なビジネスメールと同様、取引先の会社名・担当者の部署・氏名をメール本文の一番上に必ず記入しましょう。
請求書を送付する担当者の氏名がわからない場合は、会社名だけを入力し「会社名○○○御中」と敬称をつけるか、「会社名○○○ ご担当者様」と入力します。
正:会社名○○○御中
正:会社名○○○ ○○○○様
誤:会社名○○○御中○○○○様
担当者の氏名を記入して“御中”とつけると(会社名○○○御中○○○○様)、二重敬語となるため注意しましょう。
「御中」や「様」の使い分けなど、正しい宛名の書き方について迷う場合は、以下の記事をご確認ください。
関連記事:「請求書の宛名の正しい書き方は?「御中」と「様」の使い分けなど、気になるマナーを徹底解説」
③名乗り
取引先が誰から送られてきたメールなのかひと目でわかるように、会社名・部署・氏名を名乗りましょう。
普段から付き合いのある取引先の場合は「いつもお世話になっております」の書き出しではじめて問題ありません。初めてメールを送る取引先に対しては、下記を参考に丁寧な書き出しで挨拶すると、より好印象です。
<例>
平素より格別のお引き立てをいただき、御礼申し上げます。
先日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。
突然のメールでのご連絡、大変失礼いたします。
この度初めてご連絡を差し上げます、〇〇会社〇〇部の××と申します。
④謝意
依頼を受けた旨に対し改めてお礼を伝え、感謝の気持ちを表現します。いきなり請求書の内容に触れずにワンクッション挟むことで、取引先からの印象がよくなります。
⑤要旨・詳細
請求書をメールに添付した旨を、端的にわかりやすく表現します。
初めてメールする取引先の場合、添付ファイルの開封がうまくいかず、トラブルが発生したり不明点・疑問点が生じたりするケースがあります。開封や記載内容に不明点・疑問点があればいつでも連絡してほしい旨を一言加えましょう。
⑥添付内容
請求番号やファイル名を記載し、添付ファイルは何件あるのかを明確に記載しましょう。添付漏れや添付間違いにいち早く気付き、予期せぬトラブルを防げます。
⑦注意事項
振込手数料をどちらが負担するのか、明記しましょう。
取引先が振込手数料を負担する場合は、総請求額にプラスして取引先が料金を負担するため、支払ってもらうことに対してフォローを入れるのがおすすめです。「誠に勝手ながら」のようなクッション言葉のフォローを入れると、失礼な印象が薄れます。
自社が振込手数料を負担する場合は、総請求額から手数料を差し引いた金額が振り込まれます。双方で振込手数料への認識に相違が生まれないよう、明確に記載してください。
⑧署名
文章の最後には、署名として送信元である自身の身分を明記しましょう。企業名や部署、氏名だけではなく、住所やメールアドレス等の連絡先を記載します。
はじめて取引をする相手へのメールには、ひと目で情報が伝わるシンプルなデザインの署名がおすすめです。文字化けで正しく表示されないリスクを防ぐため、記号や機種依存文字を使用せず、過度な装飾を避けましょう。
【文例2】すでに請求書を送ったことがある取引先にメールで送付する場合
一度請求書を送ったことがある取引先には、請求書の送付メールを毎月送ります。ある程度文面を定型化し、金額や支払期日など変更が必要な箇所は都度変更しましょう。
<例>
件名:△月分請求書送付のご案内(①)
株式会社○○○
○○部
○○○○様
いつもお世話になっております。
株式会社▲▲▲ ▲▲部
▲▲▲▲です。(②)
□□□(案件名や商品名)請求書を添付ファイルにて
お送りさせていただきます。(③)
また、本請求書に明記させていただいた振込先へ、
●年●月●日までにお振込みくださいますよう
何卒、よろしくお願い申し上げます。(④)
なお、添付ファイルが開封できないなどの不都合な点や
ご不明な点などございました際には、お手数をおかけいたしますが、
ご一報いただきたく存じます。
ご査収の上、何卒よろしくお願いいたします。(⑤)
株式会社▲▲▲ ▲▲部
▲▲ ▲▲
住所 東京都▲▲区
TEL 03-▲▲▲-▲▲▲▲
FAX 03-▲▲▲-▲▲▲▲
E-MAIL ▲@■■.com(⑥)
文面を作成する際のポイント
①件名
初めての取引先へのメールと同様、ひと目見て請求書のメールであることがわかるよう、わかりやすい件名を記入しましょう。
正:件名 件名 ○月分請求書送付のご案内
誤:件名 お世話になっております。
何度も送付していると、件名の「〇月」部分を更新し忘れる場合があります。送信前に件名を見返す癖をつけるのがおすすめです。
②名乗り
初めての取引先へのメールと同様、ひと目で誰から送られてきたメールなのかがわかるように、会社名・部署・氏名を記載しましょう。
普段から付き合いのある取引先の場合、書き出しは最低限のマナーをおさえたシンプルな表現で問題ありません。
請求書の件とは別に打ち合わせの時間をもらったり、仕事でお世話になったりした場合は、お礼の一言を添えてください。
③要旨・詳細
どの案件に対しての請求書なのか、取引先がひと目でわかるように、商品名・案件名を必ず記入しましょう。
請求内容が複数ある場合は、間違いがないようにわかりやすくまとめます。
④支払い日の案内
請求金額の振込期日に関して、都度請求なのか月締め請求なのかにより、メールでの案内内容が変わります。
▼その都度請求する場合
取引先との商談で振込期日がすでに決まっている場合には、取り決めた期日を記載しましょう。
特に取り決めていない場合は、振込期日を設けるよう相談するか、数週間の余裕をもって期限を設けるのがおすすめです。期間に余裕をもたせることで、取引先が支払い予定を立てやすくなります。
▼月締めで請求する場合
月締めでまとめて請求する場合には、事前に取引先と締日・支払日をいつにするか、相談して決めましょう。
相談して決めた締日・支払日は、請求書・送付するメール文面に記入してください。
⑤締めの挨拶
添付ファイルがあるメールなどの文章の終わりには、「ご査収の上、何卒よろしくお願いします。」と一言添えるのが一般的です。
「ご査収」は、「添付した書類等を確認した上で、受け取ってください」と敬意をもって伝える意味があります。ビジネス文として多用されるフレーズとして覚えておきましょう。
前回請求時と請求金額が異なる場合は、料金変更の旨を一言添えるのがおすすめです。
⑥署名
文章の最後には、送信元である自身の身分を署名として明記します。企業名や部署、氏名だけではなく、住所やメールアドレス等の連絡先を明記してください。
署名に区切り線として記号や機種依存文字を使用すると、文字化けして正しく表示されない場合があります。過度な装飾を避け、ひと目で情報が伝わるシンプルなデザインを心がけましょう。役職名や住所が変わる際は、あわせて署名の修正を忘れずに対応してください。
請求書の正しい書き方や作成のマナー、Excelで作成する場合のテンプレートは、以下の記事にまとめています。参考にしてください。
関連記事:「請求書の正しい書き方は?作成方法やマナーとあわせて徹底解説」
支払い期限を過ぎても未納の場合の催促は?
まれに支払期日を過ぎても、請求金が未納というケースがあります。その場合は、入金が確認できないことをメールなどで迅速に催促しなければなりません。
未入金の状態では、取引先の担当者がメールを確認できていなかったり、対応漏れしたりしている可能性があります。取引先に悪意がなく、うっかり対応が漏れてしまっていたという場合もあるので、すぐに連絡するようにしましょう。
メールで催促する際は、文面に「催促」や「催促状」など強い印象を与える単語は避けるのがマナーです。件名には「再送信」「重要」「確認」などと記入して送信しましょう。
その際、該当する請求書を再度添付してください。
<例>
〇年〇月末日付けの請求書につきまして、〇年△月△日時点において、お支払いの確認が取れていません。つきましては、再度ご請求書をお送りさせて頂きたく存じます。
請求書をメール送付にする5つのメリット
請求書をメール送付することで、さまざまなコスト削減・リスク低減が実現できます。
代表的な5つのメリットに絞って紹介します。
郵送コストの削減
請求書を郵送で送付する場合、1通につき切手代84円が必要です。メール送付に切り替えることで、切手代が不要になります。
小さな金額に見えますが、ひと月に300通の請求書を発行している場合、1ヶ月で25,200円/1年で302,400円のコスト削減につながります。
消耗品代の削減
請求書自体を電子データ化すると、請求書発行の際に紙で出力する必要がなくなり、コピー用紙代やインクトナー代を大幅に削減できます。
コピー機をリースしているなら、印刷枚数を減らすことができ、月々の費用を安くできるでしょう。
保管費用の削減
請求書をはじめとしたデータをWEB上で保存しておけば、保管する費用の削減につながります。
そもそも帳票類は、法令で保存期間が設定されています。法人の場合、請求書は7年間の保管が必要です。
紙で請求書を出力している場合は、ダンボールやファイルなどで保存するため、かなりのスペースをとります。社内に保存するスペースがなければ、費用を投じて倉庫で保管せざるを得ません。
請求書をメール送付に切り替えることで、ファイル代や倉庫代などの保管にかかるコストを削減できます。
人件費の削減
経理・総務などのバックオフィス部門にとって、他の業務と並行して請求書の郵送準備をこなすことは、容易ではありません。どんなに急いでも、勤務時間内に終わらせられない場合は、残業する必要が出てきます。担当者への業務負担が増えると同時に、雇い主は残業代を支払わなければなりません。
請求書をメール送付に切り替えれば、紙に印刷し、三つ折りにし、封入する必要がないため、送付にかかっていた時間が少なくなります。作業時間が短くなり、人件費の削減や生産性向上が期待できます。
トラブルリスクの低減
紙の請求書を大量に出力していると、印刷機に紙詰まりが起きたり、うまく印刷されなかったりすることがあります。
また、封入枚数の多い請求書にありがちなのが、切手不足で戻ってくるケースです。切手のない請求書は自社に返送され、取引先への請求書の到着が遅れます。手作業で封入している場合は、他社と間違えて送付してしまうリスクもあるでしょう。
請求書をメール送付できれば、これらのリスクを軽減できます。取引先から連絡・指摘されるようなミスが続くと、会社の信用問題に関わります。心当たりがある場合は、メール送付を検討しましょう。
請求書をメールで送付する場合の注意点
請求書をメールで送信する場合、ビジネスマナーや文章の書き方以外に、注意すべきポイントがあります。
送付方法を誤ると、思わぬトラブルにつながりかねません。請求書をメール送付する場合は、以下の点に注意しましょう。
送付前に送り先を確認する
請求書をメールで送付する際は、メールの送信先を間違えないよう、送信ボタンを押す直前に再度宛先を確認しましょう。二度確認することで、違う取引先に誤って送付するミスを防げます。
請求書は取引情報が記載された重要な情報源です。たった1回の送信ミスが情報漏えいにつながり、最悪取引を停止せざるような事態を引き起こしかねません。
件名や添付した請求書のファイル名に記載している取引先の会社名が、送信する宛先と一致しているか、厳密に確認しましょう。
メールの文面と別に送付状は添付しない
メールで請求書を送信する際は、別途送付状を添付する必要はありません。
そもそも送付状は、郵送やFAXで請求書を送付する際に、簡単な挨拶と請求内容の概要、送付資料の枚数などをまとめた書面です。送付内容に漏れがないことを取引先が確かめるのに役立ちます。
メールの場合は、メール本文に必要な情報を掲載するので、送付状を用意しなくても失礼にあたりません。添付資料が増えることで、取引先を混乱させる恐れがありますので、必要事項はメール本文にまとめてください。
電子請求書は電子データのまま保管する
2024年1月以降、オンライン上でやりとりされたすべての電子請求書は、電子データのまま保存するよう義務化されました。請求書の電子取引における保存義務では、以下の要件を満たす必要があります。
- 請求書を訂正すると履歴が残るようにする
- 請求書を削除できないようにする
- 取引年月日・取引金額・取引先の検索が可能である
電子請求書の保存は、個人事業主・法人問わず、メールやクラウド上で請求書をやりとりする全事業主が対象です。事前に国税庁のホームページで「電子帳簿保存法」の要件を確認しておきましょう。
セキュリティの整備を行う
WEB上で請求データを扱うため、メール送信する環境のセキュリティ体制を万全に整える必要があります。
▼すぐにできる対策の例
- 添付ファイルの閲覧にパスワードをかける
- ダウンロードサービスを利用し、請求書をURL形式で送付する
- ダウンロード後はアクセス制限をかける
- 送信ミスを防ぐため、請求書のメールを送る際はダブルチェックする
上記の対策はすぐに実施できる分、対策として不十分であったり、取引先の手間を増やしたりしかねません。メール送付に切り替える前に、取引先とセキュリティ対策について相談しましょう。
メール送信時のセキュリティ対策だけでなく、保管環境のセキュリティも検討が必要です。
請求書のメール送付なら電子請求書発行システム「楽楽明細」がおすすめ
請求書をメール送付することで、紙で送付する場合に発生する切手代や紙代などのコストや手間、ミスを削減できます。
紙からメール送付への切り替えを効率的に進めたいなら、電子請求書発行システム「楽楽明細」の利用がおすすめです。「楽楽明細」は、請求書をはじめ納品書・領収書などの帳票発行を自動化させ、業務効率を向上させるクラウド型システムサービスです。請求データを取り込むだけで、「メール添付」「WEBからダウンロード」「郵送代行」「FAX」のいずれかの方法で簡単に請求書を発行できます。
「楽楽明細」はインボイス制度や電子帳簿保存法にも対応できるクラウドシステムです。インボイス(適格請求書)の発行から電子保存まで、法令対応を難なくこなせます。知識が少ない経理担当者でも、安心して利用できるのが魅力です。
- 印刷・三つ折り・封入作業が大変
- 郵便局への持ち込みが大変
- 印刷代、紙代、郵送費のコストがかさむ
- 発行先の到着指定日に間に合わない
- 封入ミスが起きてしまう
- 再発行などの個別対応が面倒
- インボイス制度や電子帳簿保存法にどう対応していいかわからない
- セキュリティ対策が不安
以上のような請求書をはじめとする帳票発行業務のお悩みは、「楽楽明細」が解決します。まずは以下よりお気軽に資料請求・お問い合わせください。
【無料】3分でわかる!電子請求書発行システム「楽楽明細」資料請求はこちら>>>
「楽楽明細」
請求書の印刷・封入・発送の作業をゼロに!
面倒な請求書発行の手間を削減します。
オススメの人気記事
- 記事執筆者紹介
- 株式会社ラクス「楽楽明細」コラム編集部
「楽楽明細」のコラムでは請求書や領収書、支払明細書などの各種帳票の発行方法や、経理業務を効率化する方法などについてご紹介します!

注目記事
96%削減できます。※
※ 月の発行件数500件の場合の月間の導入効果(ラクス調べ)


「楽楽クラウド」サービスのご紹介
「楽楽クラウド」サービスのご紹介です。
企業のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ95,000社以上のご契約をいただいています(※2025年3月末現在)。「楽楽明細」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。