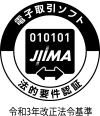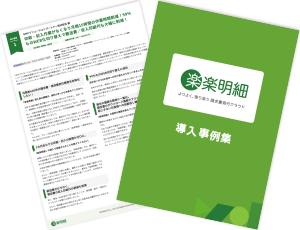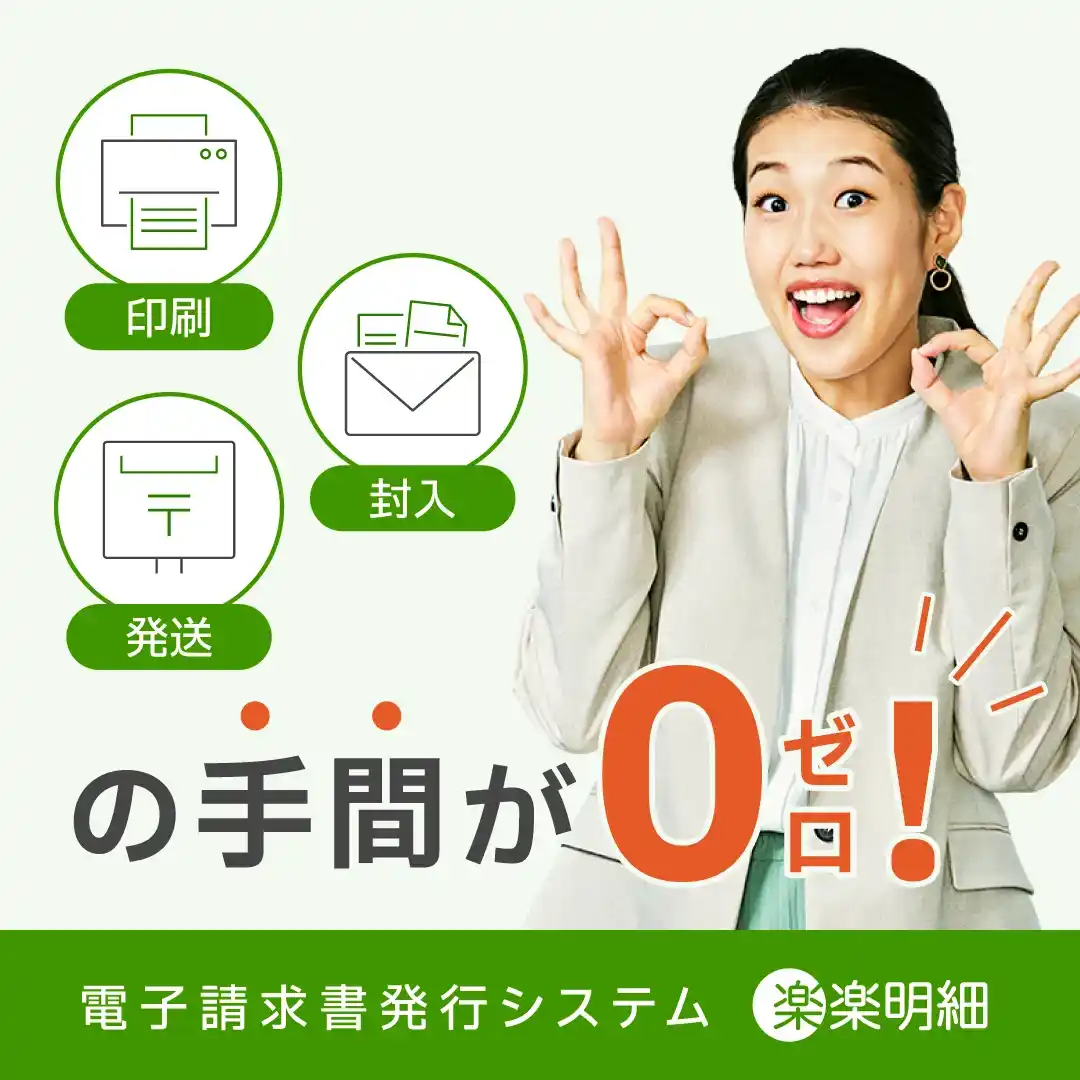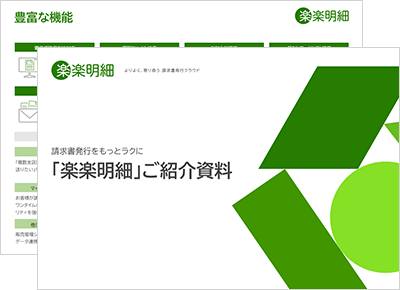企業が外注先(個人事業主等)へ支払明細書を発行する理由は?外注費と実質給与の判断基準についても解説
監修者:臼井 雄志(税理士)

外注先の企業や個人事業主に対して対価を支払う際、支払明細書を発行するケースがあります。しかし「なぜ外注先に支払明細書を発行するのか」「そもそも支払明細書の意味は何なのか」といった疑問をお持ちの経理担当者もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、支払明細書や外注に関する基礎知識、外注先に支払明細書を発行する理由について解説します。また、税務調査で争点となりやすい「外注費」と「実質給与」の違いについても取り上げましたので、自社の正しい帳簿作成に役立ててください。

この記事の目次
支払明細書とは
支払明細書とは、支払義務が確定した取引に対して発行する、料金の内訳を記載した書類です。実務では、取引内容の確認や経費を計上する際の支払金額の証明として利用されています。仮に支払金額に間違いがあった場合にも、支払明細書があれば商品・サービスの内容・数量・単価・金額などの詳細が確認できるため、訂正がしやすくなり、スムーズな取引につながります。
支払明細書の役割や書き方、エクセルを使った作成方法など、詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。
「支払明細書とは?書き方や請求書、領収書との違いなど徹底解説」
外注とは
外注とは、自社で行っていた業務の一部、又は全部を外部に委託することです。「アウトソーシング」とほぼ同じ意味で使用されています。しかし、「アウトソーシング」は自社の成長のために、「外注」は業務遂行を目的としている点に違いがあります。「アウトソーシング」は社員のリソース再配分やコスト削減・業務効率化などを目的として戦略的に執り行われるケースが多く、その成果物の納品を目的としている「外注」とは目指しているゴールが異なります。なお、「業務委託」は外注する際の契約形態の一つで、民法上は存在しない言葉です。
外注のメリット
外注を利用するメリットには、次のようなものがあります。
① コア業務に集中できる
自社の従業員や経費をコア業務に集中させることができます。
② 対応範囲を広げることができる
自社の従業員でまかないきれない商品やサービスの受注を受けた際、専門知識やノウハウを持つ外部の法人や個人に外注することで対応が可能になります。従前の自社のできる業務の範囲から、幅を広げることができます。
③ コストを削減できる
従業員を高度な受注に対応できる人員に育てるには、多くの時間と教育費が発生します。社会保険料なども含め、人材にかかる費用は、外注で業務を行うのみの場合と比べて1.5倍~2倍ほどかかると言われています。
しかし、アウトソーシングや外注では、適切に仕事をしてくれなかった場合や、成果が達成できなかった場合には、支払いをしないことや、支払額を減額するような契約を結ぶことも可能です。正社員の給与は変動させることが難しいですが、アウトソーシングや外注では成果物に応じて支給しやすいのが特徴です。
また、社会保険料の負担もなく、外注費に上乗せして支払った消費税は、仕入税額控除として消費税等の納税額を減少させることができます。そのため、人件費を抑えてコスト削減が図れるでしょう。
外注費と給与の税務上の取扱い
ここで、たびたび税務調査の争点となる、「外注費と給与の法律上の取り扱いの違い」について解説します。業務の対価として支払った額を給与として計上した場合と、外注費として計上した場合では以下の違いがあります。
1. 支払いに対する消費税の取り扱い
消費税の課税事業者、かつ簡易課税ではなく原則課税による仕入税額控除の計算を行っている場合には、以下のような違いがあります。
- 外注費は課税仕入れの取り扱いです。上乗せされた消費税は仕入税額控除が可能なため、納税額を減らすことができ、結果的に納税者に有利になることもあります。
- 給与は不課税仕入れの取り扱いです。仕入税額控除はできないため、外注費と比較すると納税額が多くなります。
2. 源泉徴収義務の有無
- 外注費は源泉徴収が課されません。ただし、士業や芸能人、デザイナー等一部の外注費(報酬)には、報酬源泉といわれる源泉徴収が課されます。報酬源泉なので、給与の源泉所得税とは税率が異なる点に注意しましょう。また、外注先が適正に確定申告をしていなければ給与と判断される可能性が高くなるため、取引先に税務調査が発生した場合のリスクも考え、確認しておくという方法もあります。
- 給与は低額な場合を除き、源泉徴収義務があります。給与計算には源泉所得税の計算がついてきます。そのため、支払うたびに税率にあった源泉徴収をしなければならず、企業は預かった源泉所得税を納める義務があるのです。
3. 社会保険の加入義務の有無
- 外注費は加入義務がなく、事業主負担分もありません。
- 給与は法人であれば正社員なら加入義務があり、事業主負担分も発生します。また、正社員ではなくパートやアルバイトでも、勤務形態と企業の規模によっては加入が必要な場合があります。
外注費を給与と認定された判決とペナルティ
このように、税務上の取扱いを確認してみると、業務への対価の支払いは外注費として計上する方が有利に思えます。では、形式上「請負契約書」を作成して、消費税を上乗せした請求書や支払明細書をもとに外注費と処理してもよいのでしょうか。結論から言えば、委託の形態に合わせて適切に処理をすべきです。万が一処理を誤ると、税務調査で指摘され「ペナルティを受けるリスク」があります。
過去、電気工事を営む会社が計上した外注費が、税務調査において給与と指摘される事件がありました。この事件は高等裁判所においても給与と認定されたため、給与に対する源泉所得税徴収漏れ、給与は不課税取引であるため仕入税額控除過大、そしてこれらに伴う追徴課税が生じ、多額の金員を納付することとなりました。(平成20年4月23日東京高等裁判所判決)
外注費を給与と判定された場合、消費税の取り扱いがかわるため修正申告が必要となる場合があります。また、修正申告には延滞税が課されるため、上記の判決事例にある通り、通常の消費税の納税額よりも多くの現金支出が発生します。
なお、外注先が適切に確定申告していない場合、契約の内容や実際の業務内容と状況、支払方法により「適切」と判断されれば、外注元である企業にペナルティはありません。しかし、適正なものと判断できなければ恣意的に申告していないと判断され、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」が課される可能性があります。

外注費か給与かの判断基準
次に、外注先への支払いが外注費か給与に該当するかどうかの判断基準について見ていきましょう。
形式的には、役務提供の対価として受ける金銭等の性質が、雇用契約もしくはこれに準ずる契約に基づく対価である場合は「給与」、請負契約、もしくはこれに準ずる契約に基づく対価である場合は「外注費」として取り扱われます。さらに、その区分が明らかでないときは、業務の実態を外注費の判断基準に照合して総合的に勘案して判断されます。国税庁のホームページを参考に分類すると、次のようになります。
| 判定基準 | 給与 | 外注費 |
|---|---|---|
| その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。 | ✕ | 〇 |
| 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。 | 〇 | ✕ |
| まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。 | 〇 | ✕ |
| 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 | 〇 | ✕ |
例えば、自分ではない誰かが変わってその業務をできるのであれば、「従業員である必要がない=外注でもいい」という判断になるため、外注費の扱いになります。
参考:国税庁「第1節 個人事業者の納税義務」
外注費を給与と認定されないために支払明細書を発行する
税務調査の際に指摘される内容で多いのが、「外注費ではなく給与である」というものです。給与と認識されれば、源泉徴収が必要になります。源泉徴収が必要となれば、延滞税も課税され金額によっては多額になることもあります。また、消費税の課税事業者の場合は、消費税も納税する必要が出てくるでしょう。給与ではなく外注費として認めてもらうために必要な対策があります。
外注費を給与と認定されないための対策
対策方法のポイントは2つあります。
1つめは、「総合勘案して外注費に該当すると判断されるよう、形式上の要件である『請負契約書の締結』を行うこと」です。外注費かどうかの判断には「取引先が独立して事業を行っているかどうか」という点も勘案されますが、「独立」の定義は明確にされていません。よって、まずは形式上の要件を満たすことがポイントになります。
2つめは、「対価にかかる請求書等を作成していること」です。東京局個人課税課速報第28号(平成15年7月)に掲載されている判定検討表の判定事項の中の一つに「その対価にかかる請求書等の作成がされているか」という項目があることから、給与と区別するためには、請求書が必須となります。なお、請求書の発行は、外注先が発行する必要がありますが、対価が「時給計算」になっている場合は雇用関係があると見なされ、給与と認定される場合がありますのでご注意ください。
支払明細書の発行で、外注費を給与と認定されるリスクを軽減
外注先が、請求書の作成に関して十分な知識がない個人事業主である場合は注意が必要です。外注先となる場合であっても、給与と認定される可能性のある記載を意図せずして、請求書に記載してしまうこともあります。この場合、発注元の企業が外注先に対して適切な支払明細書を交付し、これに基づき外注先が請求書を作成するよう設定すれば、支払った金額が意図せず給与と認定されるリスクを低くすることが可能になるでしょう。
まとめ
外注先への支払いが誤って給与とみなされないために、業務の実態も外注費の判断基準に沿っているか確認する必要があります。また、外注先が請求書の作成に関して十分な知識がない場合、発注元の企業が外注先に対して適切な支払明細書を交付することもリスクの低減に役立つでしょう。
外注先に適切に支払明細書を発行する上では、電子帳票発行システム「楽楽明細」がおすすめです。「楽楽明細」は、支払明細書や請求書など、あらゆる帳票を簡単に電子発行できます。
電子発行すれば、支払明細書を発行する際の手間やコストを削減できるだけでなく、再発行や修正が必要となった際にすぐに対応ができるといったメリットもあります。ぜひこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。
【支払明細にも対応】電子請求書発行システム「楽楽明細」の資料請求はこちら>>>
「楽楽明細」
請求書の印刷・封入・発送の作業をゼロに!
面倒な請求書発行の手間を削減します。
オススメの人気記事
- 監修者税理士
- 臼井 雄志
税理士、臨床工学技士、行政書士。大学は臨床工学科へ進学し、臨床工学技士免許を取得。クリニックで透析治療に従事した後、税理士法人に勤務しながら税理士試験を受験し、税理士資格を取得。
現在は医科、歯科、介護、薬局の税務を中心とした税理士事務所を経営。
臼井雄志税理士事務所
注目記事
96%削減できます。※
※ 月の発行件数500件の場合の月間の導入効果(ラクス調べ)


「楽楽クラウド」サービスのご紹介
「楽楽クラウド」サービスのご紹介です。
企業のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ95,000社以上のご契約をいただいています(※2025年3月末現在)。「楽楽明細」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。