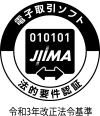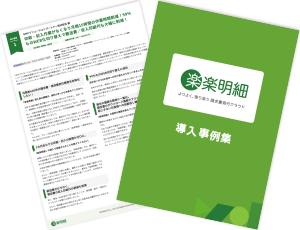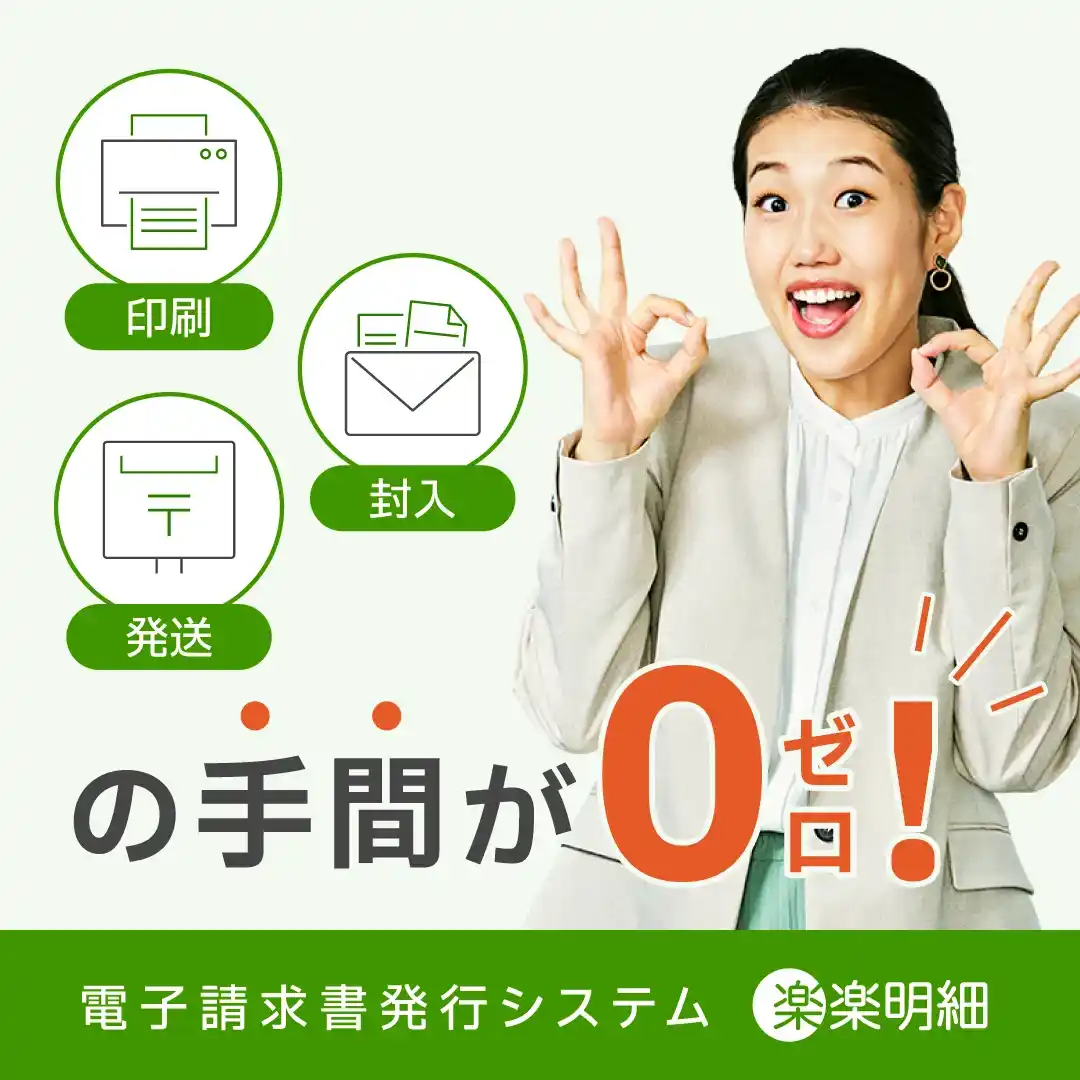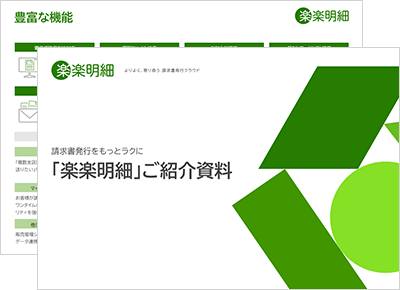領収書電子化のやり方とは?注意すべき法制度の要件や運用時のポイント

領収書を電子化すると、発行側・受領側のどちらの企業にとっても、コスト削減や業務効率化などの効果が期待できます。それでは、具体的にどのような方法で電子化を進めればよいのでしょうか。
この記事では、領収書電子化の方法と具体的な手順を解説します。領収書を電子化する上で理解しておきたい「電子帳簿保存法」の基礎知識や、運用時のポイントなどをまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
領収書の電子発行についてさらに詳しく知りたい担当者の方は、以下の関連記事も併せてご覧ください。

この記事の目次
領収書を電子化する上で重要な「電子帳簿保存法」
領収書をはじめとした国税関係帳簿書類は、「電子帳簿保存法」の要件を守れば電子化することができます。取引を証明する書類は、法律に則って適切に保存しましょう。
電子帳簿保存法には、「スキャナ保存」「電子取引データ保存」「電子帳簿等保存」という3つの保存区分が設けられています。
- スキャナ保存…紙で授受した書類をスキャンして電子データとして保存すること
- 電子取引データ保存…電子取引で授受したデータを保存すること
- 電子帳簿等保存…電子データで作成した帳簿・書類をデータのまま保存すること
データを保存する際の要件は保存区分によって違いがあります。例えばスキャナ保存の要件を見ると、「訂正・削除の事実を確認できるシステムを使用すること(=真実性)」や「ディスプレイやプリンターなどを備え付けること(=可視性)」「検索機能を確保すること(=検索性)」などのさまざまな要件を守る必要があります。
保存区分ごとの要件について詳しくは国税庁のサイトおよび以下の関連記事でご確認ください 。関連記事では、電子領収書と電子帳簿保存法についてわかりやすく解説しています。
出典:国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」
関連記事:「領収書を電子化する際に守るべきルールとは?法的効力や注意点」
領収書を電子化する主な2つのやり方
領収書を電子化する方法には「スキャナで電子化する方法」と「システムを使って電子化する方法」があります。詳しく見ていきましょう。
スキャナで電子化する
主に領収書の受領側における電子化の方法です。取引先から紙で受領した領収書を、複合機やプリンターのスキャン機能で読み取ったり、社用スマートフォンのカメラで撮影したりして、電子画像として保存します。
ポイント
スキャナによる電子化は、すでにオフィスにある複合機やプリンターで対応できるため、導入時の負担を抑えながら電子化を進められます。
ただし、その際は電子帳簿保存法の要件に合わせてスキャン作業やファイル管理のオペレーションを構築しなければなりません。例えば、不正な改ざんを防止するためにタイムスタンプ(=改ざん防止の技術)を付与したり、訂正・削除履歴を確認できる専用システムを導入したりする必要があります。
システムやソフトを使って電子化する
主に領収書の発行側における電子化の方法です。具体的には、専用の電子帳簿発行システムを使って領収書を発行したり、エクセルなどのソフトを使って作成したりする方法があります。
ポイント
システムを使った電子化の場合、専用の電子帳票発行システム を導入する方法をおすすめします。専用のシステムであれば、領収書発行業務全体を効率化できるのです。エクセルとは異なり、領収書発行業務の効率化につながります。自動作成によって領収書作成時のデータ入力や確認がラクになるのがメリットです。また、オンラインで発行するため、印刷・三つ折り・封入・郵送といった作業が不要となります。
また、電子帳簿保存法に対応した電子帳票発行システムであれば、最新の法要件を満たした運用をすぐに実現できます。 エクセルの場合は、自社で法要件を満たしているか確認する手間がかかります。一方、電子帳票発行システムなら最新の法要件を満たした運用を楽に始められます。将来的な法改正時の対応も簡単です。
システム導入には初期費用や月額費用など一定の費用がかかるものの、業務全体の改善が期待できるので、投資に対して十分な効果を得られるでしょう。

領収書を電子化するメリット・デメリット
領収書を電子化すると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。それぞれ確認していきましょう。
メリット
ペーパーレス化によりコストを削減できる
領収書の発行側・受領側ともに、ペーパーレス化でコスト削減を実現できます。発行側は、紙代・インク代・封筒代・切手代・印紙税などを大幅に削減可能です。一方、受領側では原本のファイリングが不要となるので、ファイルや保管棚などの備品にかかる経費を削減できます。
事務処理の負担を軽減できる
領収書を電子化すると、書類を授受する際の事務処理の負担が軽減され、発行側・受領側の双方にメリットがあります。発行側は、専用システムを活用することで領収書発行が自動化され、手続きのスピードアップが期待できます。受領側は、郵送によるタイムラグがなくなり、速やかに領収書を受領することが可能です。また、万が一書類の内容に不備があった場合、修正のやり取りもオンラインでスムーズに行えます。
保管に必要なスペースを削減できる
発行側は領収書の控え、受領側は領収書の原本を保管するスペースを削減できます。オフィスに書類の保管場所を確保している場合は、電子帳簿保存法の要件を守って電子化すれば、不要な紙の書類を破棄することができるのです。空いた保管スペースを別の業務で有効活用できます。
デメリット
スキャナやシステムの導入に時間と費用がかかる
領収書を電子化する場合、発行側・受領側ともに機器やシステムの導入で費用が発生する可能性があります。具体的には、発行側では専用システムの導入・運用費用、受領側はスキャン機能を搭載した複合機やプリンターの導入・設置費用などがかかります。ただし、いずれのケースでも業務効率化によって十分な費用対効果を得られるケースがほとんどです。
社内規程や業務フローを整備する手間がかかる
領収書を電子化する際は、発行側・受領側が連携して、やり取りの手順などを再整備する手間がかかります。導入前後は社内外の調整で一時的に現場の負担が増えやすいのが注意点です。
電子領収書のメリット・デメリットや、スムーズに移行する方法は、以下の関連記事で解説しています。こちらも併せてご覧ください。
関連記事:「電子領収書のメリット・デメリット|スムーズに移行する方法とは」
領収書を電子化するなら電子帳簿保存法対応のシステムが安心!
今回は、領収書を電子化するやり方を解説しました。領収書を電子化する際は、電子帳簿保存法の要件を守ることが大切です。自社と取引先の双方にコスト削減や業務効率化のメリットがもたらされるので、紙ベースで運用しているならぜひ取引のデジタル化を検討してはいかがでしょうか。
特に領収書の発行側は、専用システムを活用することで、発行業務全体の効率化を実現できます。なかでもおすすめなのは、簡単操作で領収書を電子発行できるシステム「楽楽明細」です。
魅力➀電子帳簿保存法へスムーズに対応できる
システムを導入するだけで電子帳簿保存法の要件を満たした領収書の電子発行ができます。また、インボイス制度にも対応しているため、業務効率化やコスト削減と合わせて法制度への対応も実現できます。
魅力➁シンプルで簡単に操作しやすい
シンプルでわかりやすい画面設計のため、現場担当者が直感的に操作できます。システムが得意ではない方にも簡単にご利用いただけるので、現場に定着しやすいのがポイントです。
魅力➂導入前後のサポート体制が充実
導入前の運用提案やフォロー、運用開始後のメールや電話での問い合わせ対応など、サポート体制が充実しています。初めてのシステム導入も安心してお任せいただけます。
「楽楽明細」の特長や導入メリットなどの詳細な情報は、無料の資料でご案内しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
【無料】3分でわかる!電子請求書発行システム「楽楽明細」資料請求はこちら>>>
「楽楽明細」
請求書の印刷・封入・発送の作業をゼロに!
面倒な請求書発行の手間を削減します。
オススメの人気記事
- 記事執筆者紹介
- 株式会社ラクス「楽楽明細」コラム編集部
「楽楽明細」のコラムでは請求書や領収書、支払明細書などの各種帳票の発行方法や、経理業務を効率化する方法などについてご紹介します!

注目記事
96%削減できます。※
※ 月の発行件数500件の場合の月間の導入効果(ラクス調べ)


「楽楽クラウド」サービスのご紹介
「楽楽クラウド」サービスのご紹介です。
企業のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ95,000社以上のご契約をいただいています(※2025年3月末現在)。「楽楽明細」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。