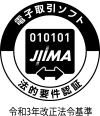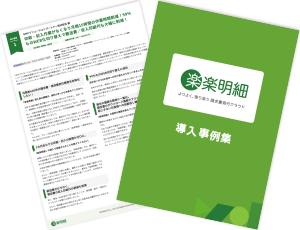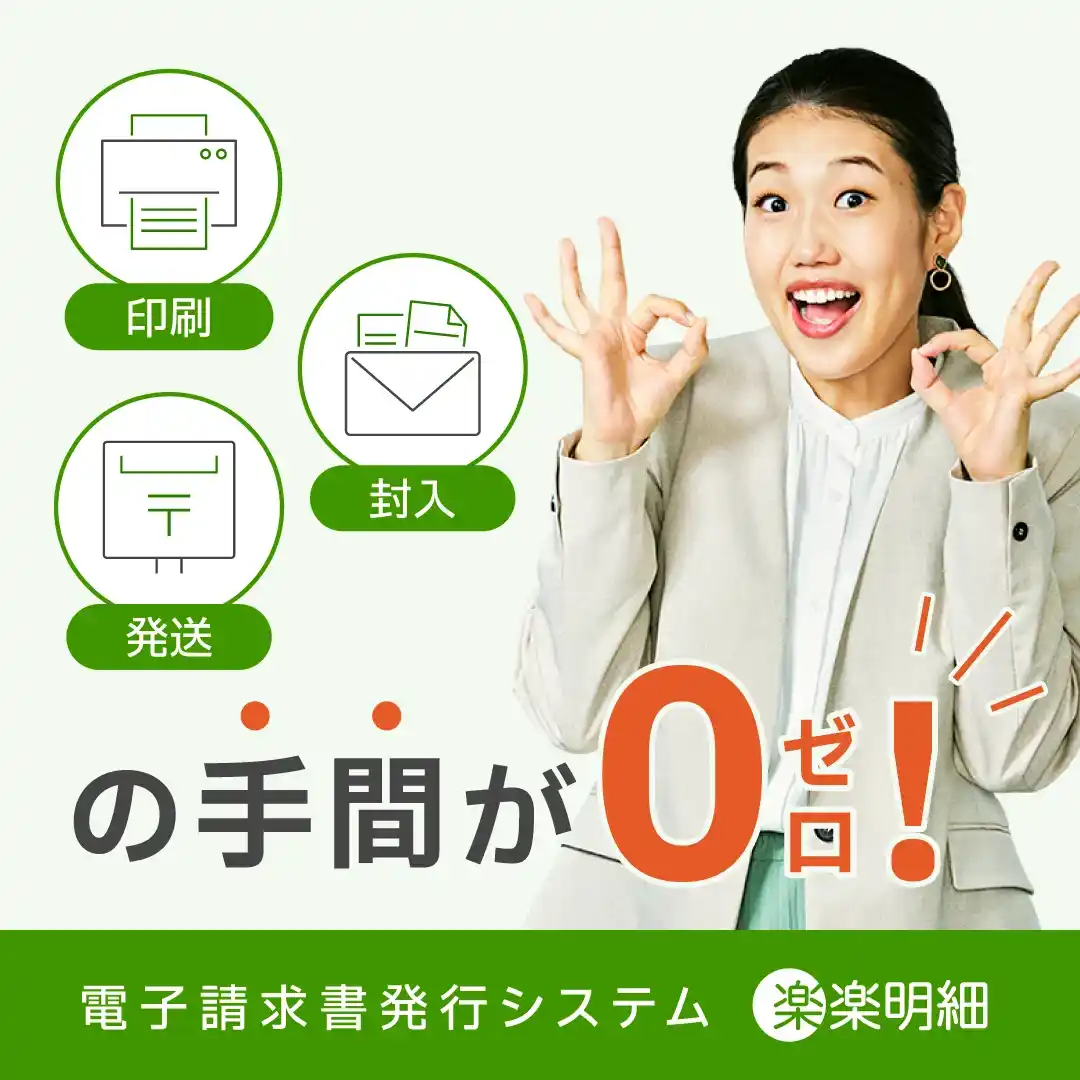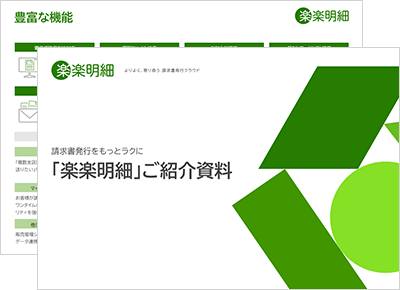領収書の正しい書き方は?宛名や収入印紙の金額、消費税の取扱など詳しく解説
監修者:川口 拓哉(税理士)

ビジネスの現場で日常的にやり取りする書類の一つである領収書について、大枠の知識はあっても細かい点が分からないまま実務をこなしている経理担当者の方もいるのではないでしょうか。
この記事では、「領収書の正しい書き方を知りたい」「他部署や上司から領収書の確認を依頼されたが何をチェックすればよいかわからない」という経理担当者に向けて、領収書に記載が必要な項目やその正しい書き方、その他領収書を発行する際の注意点など、詳しく解説します。

この記事の目次
領収書の基礎知識
まずは領収書の基礎知識についておさらいしましょう。
領収書とは、お金を受け取った証しとして、お金を受け取った側が発行する書類です。ビジネス上では、取引をおこなった際、お金を受け取ったことを証明するものとして欠かせない書類の1つです。
領収書の役割
前述の通り、領収書は取引における金銭のやり取りの証明書としての重要な役割をもちます。そのため、領収書には、受け取った金額はもちろん、日付や何に対しての金銭のやり取りなのか、発行側の企業名などの詳細、領収書を受け取った側の企業名や氏名を明確に記載しなければなりません。このような金銭取引の証拠となる書類は「証憑書類」(しょうひょうしょるい)に分類され、領収書の他に納品書や見積書が該当します。
領収書は、お金を払った側が家計簿をつけるため、あるいは商品に不具合があったときに購入を証明するためといったように、個人的に保管するだけではありません。例えば会社経費として計上したり、確定申告時に使用したりとさまざまな用途に利用されます。いずれも金銭の受け取りを証明する際に必要な重要書類となります。そのため、実際におこなわれた金銭のやり取りを忠実に記載しなければなりません。
領収書の発行義務
では、領収書の発行義務は法律で定められているのでしょうか。調べてみると、民法第486条に「弁済をする者は弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。」という規定はありますが、この規定は任意規定に分類されています。そのため、両者で「領収書の発行は必要ない」と合意があれば、領収書を発行する必要はありません。なお、インボイス制度開始後は、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときはインボイスを交付する義務を負うこととなります。
参考:国税庁「インボイス制度QA問24」
また、クレジットカードで支払った場合には、金銭を要求しクレジットカード処理した側に領収書の発行義務は発生しません。なぜなら、クレジットカードでの支払いは実際の金銭の取引ではないからです。クレジットカード会社が代金を立て替えている形となるため、領収書の発行義務は発生しません。しかし、クレジットカードでの支払い時に発行される利用控えはクレジットカードで支払った証明書となるため、一般的には領収書の代用として扱うことが可能です。
領収書の保管義務
法人や個人事業主には、領収書を一定期間保存する義務が課せられています。
法人の保存期間は、原則としてその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間です。ただし、青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度等においては、10年間となります。
個人事業主の保存期間は、青色申告か白色申告かで異なります。青色申告の場合の保存期間は確定申告期限の翌日から7年間で、白色申告の場合は5年間です。
参考:国税庁「帳簿書類の保存期間」「記帳や帳簿等保存・青色申告」
領収書の書き方・ポイント
次に、領収書の書き方についてご紹介しましょう。文具メーカーや100円均一などで販売している領収書を使う方法もありますが、エクセルなどで領収書を自作することも可能です。
領収書に記載が必要な項目は以下6点です。それぞれの項目の書き方とポイントを解説します。
②宛名
③金額
④但し書き
⑤内訳
⑥発行者
①取引年月日の書き方
取引年月日は「XX年●●月▲日」といった形で記載します。月日だけだと後から見たときに何年の分かわからなくなるので、必ず年も明記しましょう。年は和暦表記でも西暦表記でも、どちらでも問題ありません。
②宛名の書き方
宛名は「〇〇株式会社御中」や「▲▲様」と記載します。他の書類などで「株式会社」を「㈱」と略す場合もありますが、領収書においては省略せずに正確に明記することが望ましいでしょう。また、領収書の宛名書きに「上様」と書くことも定着していますが、消費税の仕入税額控除の関係で問題となるケースもあるため、氏名や企業名を正しく記入しましょう。
③金額の書き方
金額の改ざんがないように以下のいずれかのように記載しましょう。領収書に記載する受け取った金額、すなわち消費税を含めた総合計を必ず記載してください。
<例>
\○○○,○○○※
\○○○,○○○-
金○○○,○○○也
④但し書きの書き方
但し書きとは、金額と共に記載する必要事項の1つであり、何に対する金銭を受領したのかを大まかに記載する必要があります。例えば事務所で使用する固定電話を販売したときの領収書を発行する場合は、「但し、電話機本体の代金として、上記金額正に領収いたしました」と記入します。
但し書きとして「お品代」と記載する慣習も広く見られますが、「お品代」だけだと領収書の内容が分からないため、税法上は具体的な品目を記載することが望ましいと考えられます。
なお、印紙税の関係で、クレジットカード払いの場合の領収書には「但し、クレジットカード利用」と必ず記載するようにしましょう。実際の取引がクレジットカード払いであったとしても、その旨を領収書に記載しないと印紙税の課税文書に該当する恐れがあるのでご注意ください。
参考:国税庁「質疑応答事例」
⑤内訳の書き方
一枚の領収書に消費税の軽減税率対象品目(食品や定期購読契約に基づく新聞等)とそうでないものが混在している場合は、合計金額の他に税率ごとの内訳を記載する必要があります。たとえば、1,080円のお菓子と1,100円の食器を販売して2,180円の領収書を発行する場合は、内訳として「8%対象:1,080円(消費税込、軽減税率対象品目)、10%対象:1,100円(消費税込)」と記載する必要があります。
また、インボイス制度開始後のインボイスでは、内訳欄に税率ごとに区分した消費税額を記載する必要があるため、内訳欄の記載事項が更に増加します。たとえば、上記の例の場合だと、それぞれの消費税額(80円及び100円)を追加で記載することになります。
⑥発行者の書き方
トラブルを避けるために発行した側の情報(会社名、氏名または名称)は正しく記載しましょう。なお、発行者による押印は義務付けられていませんが、実務上は押印するのが一般的です。
また、上記の必須項目の記載に加え、5万円以上の紙の領収書には収入印紙の貼付が義務付けられています。収入印紙については、次章「領収書に貼る収入印紙の金額と取扱ルール」で詳しく解説します。
なお、インボイス制度に対応した領収書の書き方や、インボイス制度における領収書の扱いについては、下記記事で詳しく解説しています。
関連記事:インボイス制度で領収書の扱いはどう変わる?インボイスと簡易インボイスの違い・正しい書き方を詳しく解説

領収書に貼る収入印紙の金額と取扱ルール
「印紙税法」により、領収書には収入印紙を貼ることが法律で定められています。5万円未満までは非課税であるため、収入印紙を貼る必要はありませんが、受け取り金額が5万円以上の場合は、以下のとおりに収入印紙の貼付が必要です。
| 受け取り金額 | 収入印紙の金額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 600円 |
| 300万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円超2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円超3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円超5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
| 記載金額のないもの | 200円 |
出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)」
また、5万円以上の受け取り金額にも関わらず、収入印紙を領収書に貼っていない場合には印紙税法第20条に規定されているように、原則として、本来必要であった印紙の3倍にあたる金額を支払わなければならなくなります。あらかじめ、貼り忘れのないように注意しましょう。
収入印紙の貼り方や貼る際の注意点、消印の方法などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:収入印紙とは?領収書や契約書に貼る際の金額や購入場所、貼り方など徹底解説
領収書の割印の役割とルール
領収書に収入印紙を貼付した場合は、消印(一般的には「割印」とも呼ばれます)を行う必要があります。印紙税法において、「印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならない」とされていることから、消印は必ず行うようにしましょう。また、消印があることは正式に領収した証しともなり、改ざんを防ぐ役割も担います。
消印を行う印鑑の種類に決まりはありません。支払いを担当する人の個人名の印鑑、代表者名の印鑑、経理担当者名の印鑑など、どのような印鑑を使用しても構いません。また、実印ではなくシャチハタ印でも問題ありません。
参考:国税庁「質疑応答事例 印紙の消印の方法」
領収書を再発行する際の注意点
領収書は金銭のやり取りの証として発行されるため、むやみな再発行は避けるべきと考えられています。なぜならば、2枚同じ内容の領収書が世の中に存在することになるからです。場合によっては、2回金銭のやり取りが行われていると受け取られかねませんし、二重発行した領収書が不正な目的で利用されるリスクを負うことにもなります。更に、二重発行に偽造が絡むと刑法上の文書偽造の罪に問われたり、税務調査で重加算税を課せられたりするペナルティを負うことになるリスクもあります。
しかし、領収書の再発行を拒否できない場合や、紛失の理由などから双方の同意があれば領収書に「再発行」と記載することを条件に領収書を再発行するケースもあります。再発行する場合は、二重の発行ではない「再発行」であることを、直接領収書にしっかりと明記しましょう。
領収書をPDF(電子データ)で発行すれば収入印紙は不要?
近年、メールやWEB上で書類をやり取りするケースが増えてきましたが、PDFファイルで発行された領収書の場合、国税庁のホームページにも記載がある通り「実際には課税文書は交付されていないため、印紙を必要としない非課税である」と判断されます。そのため、PDFファイルで発行された領収書には印紙が必要ありません。そのため、PDFファイルによる領収書の発行は、節税対策としても有効とされています。
参考:国税庁「文書回答事例」
なお、領収書をPDF化(電子化)するメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:電子帳簿保存法改正で領収書の扱いはどう変わる?電子化するメリットと注意点についても解説!
領収書を電子発行するなら「楽楽明細」
「楽楽明細」は領収書をはじめ、請求書や見積書、支払明細書など、ビジネスで必要となるあらゆる書類帳票をWEB発行するシステムです。領収書をWEB発行すれば、手書きの手間や印刷・封入・発送といった発行の手間を削減できるだけでなく、前述の通り、収入印紙を貼る必要がないため、コスト削減にもつながります。さらに郵送で発生するタイムラグや紛失の防止など、発行側にとって大きなメリットがあります。取引先である受取側も、ネット環境さえあれば時間や場所を選ばず書類をスムーズに受け取れるというメリットがあるため、双方に利便性は高いといえます。
まとめ
今回、領収書の基礎知識に加え、領収書の書き方、収入印紙の金額、再発行の注意点などを解説しました。領収書は記載事項や記載上の注意点が多いので、是非この記事を参考に、正しい記載の仕方に留意して領収書を発行しましょう。
また、領収書を電子データで発行すれば作成や発送の手間削減、印紙税の節税につながるため、この機会に領収書の電子発行をご検討されてみてはいかがでしょうか。
「楽楽明細」
請求書の印刷・封入・発送の作業をゼロに!
面倒な請求書発行の手間を削減します。
オススメの人気記事
- 監修者税理士
- 川口 拓哉
税理士(名古屋税理士会)。2017年の税理士試験で官報合格。
法人及び個人の確定申告書作成、協会における相談対応、Webメディアでの記事執筆や監修などの経験を有する。川口拓哉税理士事務所代表。
川口拓哉税理士事務所
注目記事
96%削減できます。※
※ 月の発行件数500件の場合の月間の導入効果(ラクス調べ)


「楽楽クラウド」サービスのご紹介
「楽楽クラウド」サービスのご紹介です。
企業のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ95,000社以上のご契約をいただいています(※2025年3月末現在)。「楽楽明細」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。