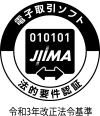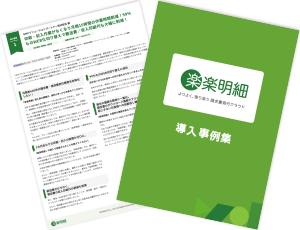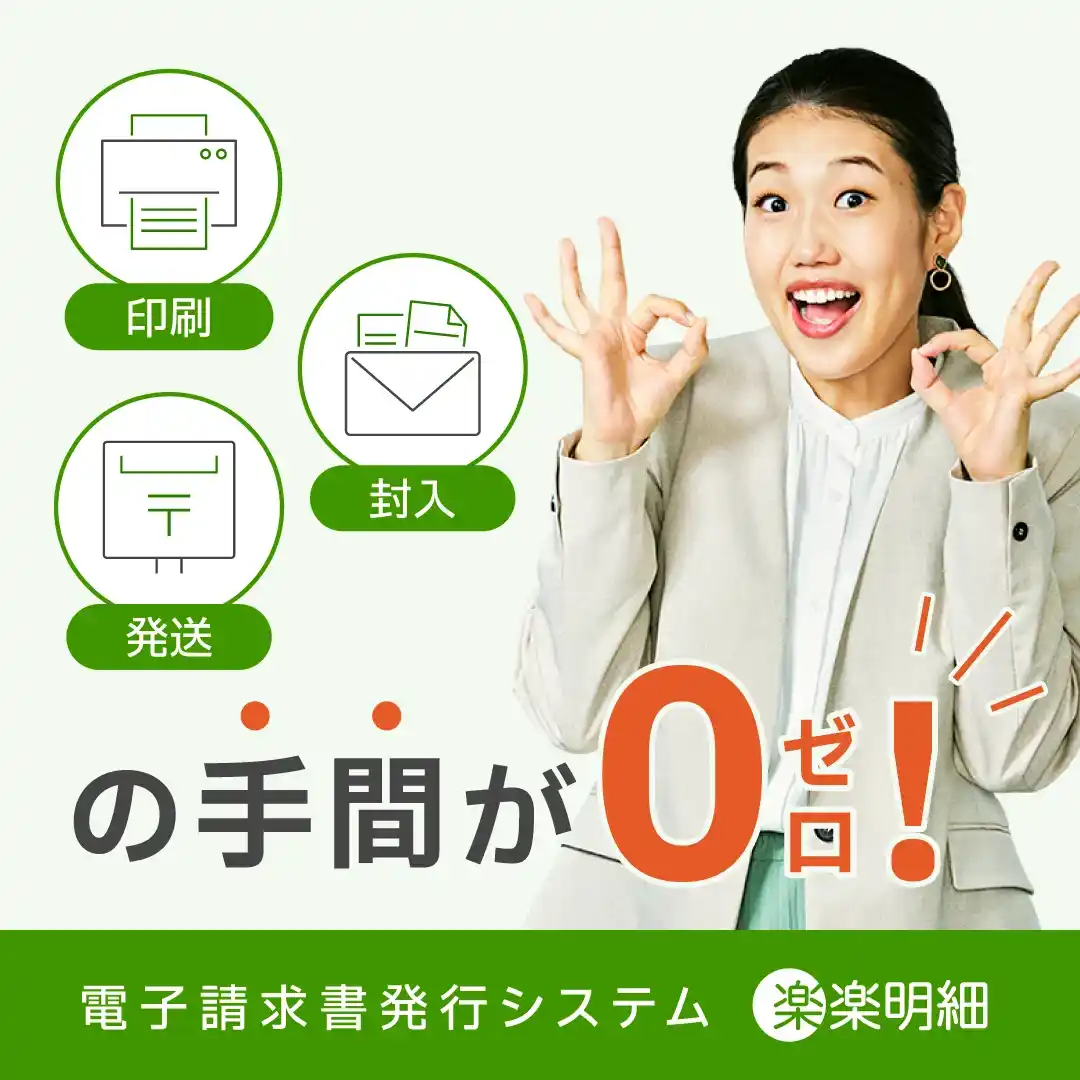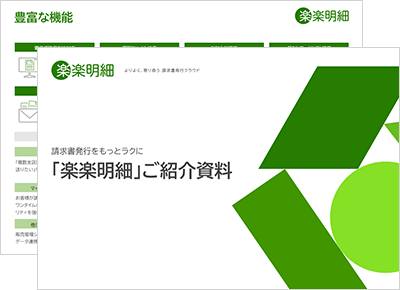領収書は再発行してもよい?依頼された際の対応方法や再発行の注意点

領収書は、支払者から金銭を受領した事実を証明する証憑書類です。企業間のお金の流れに関わる重要な書類であるため、紛失や破損は避けなければならず、原則として再発行が認められないことが多いです。
しかし、やむを得ない事情で取引先から領収書の再発行を求められた場合は、経理担当者はどのように対応すればよいのでしょうか。
この記事では、領収書の再発行に関する基礎知識を解説します。領収書の再発行を依頼された際、対応方法に悩んでいる経理担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の目次
領収書の再発行は原則避けるべき
取引先から領収書の再発行を求められた場合、実は必ずしも対応する必要はありません。領収書の再発行について、法律上の対応義務がないためです。
そもそも、領収書の再発行にはリスクが存在するため、一般的に安易に応じるのは望ましくないとされています。
具体的には、再発行した領収書を架空取引の売上計上や経費の水増しに不正利用される危険性などが考えられるでしょう。悪意をもった領収書の二重発行に加担しないよう、発行側は注意しなければなりません。
まずは、できるだけ領収書の再発行には対応しないように、記載ミスや変更が発生しないよう努めることが重要です。また、再発行の依頼を受けた際には、領収書を再発行する以外の方法がないか探るところから始めましょう。
領収書の再発行に対応する主なケース
前述した通り、二重計上や不正利用防止の観点から、領収書の再発行は必ずしも応じる必要はありません。その一方で、何らかの理由で対応する場合は、不正につながらないように配慮して対応しましょう。
企業が領収書の再発行に対応する主なケースとして、以下のパターンが挙げられます。これらのケースに該当する場合は、慎重に領収書の再発行に応じるとよいでしょう。
取引先との関係性を考慮しなければならない場合
一つ目は、重要な得意先から領収書の再発行を求められるパターンです。依頼に応じない場合に関係悪化が懸念されるのであれば、企業の方針次第では再発行に応じる可能性があります。また、信頼できる取引先であれば取引の実態を把握しやすく、不正利用のリスクが少ないと判断できることもあるでしょう。
発行側の不備が原因の場合
二つ目は、発行側の過失が原因で領収書の再発行を求められるパターンです。例えば領収書の記載内容に誤りがある場合など、発行時の不備による再発行の依頼は早急に対応しましょう。
再発行の流れは、次の見出しで解説するため参考にしてみてください。

領収書を再発行するときの対応方法
ここでは、領収書を再発行するときの対応方法を解説します。社内規定で領収書の再発行が認められている場合は、以下の流れで対応しましょう。
STEP1. どのような経緯で再発行を依頼しているのか確認する
まずは取引先が領収書の再発行を求める経緯を確認してください。相手側の過失による紛失や破損が原因の場合は、先方社内で対応できる可能性があります。「出金伝票」や「支払証明書」による経費精算ができないか確認してみましょう。
一方、発行側の不備による再発行依頼であれば、謝罪し、早急に再発行の手続きを進めます。
STEP2. 取引内容を確認する
領収書の再発行に応じる場合は、該当の取引がどれか、過去の取引内容を遡って確認します。以下を参考に、取引先へ再発行が必要な領収書の情報を問い合わせましょう。
▼取引内容の突合に必要な情報
- 領収書の発行日
- 取引内容(購入商品・サービス名、金額など)
- 発行先
- 支払い方法(現金・クレジットカード・振込など)
STEP3. 領収書の再発行を行う
社内規定に従って領収書の再発行を行います。その際は、書類に但し書きで再発行である旨を明記してください。再発行の事実を明確に示すために、領収書の目立つ位置に「再」や「再発行」などの文字を追記しましょう。
STEP4. 再発行の記録を帳簿に残す
再発行した領収書や証明書の控えは、元の領収書や取引記録と紐づけて保管します。再発行した事実を発行履歴の記録に残すことで、不正利用などのトラブル防止につながります。
領収書を再発行する際の注意点
やむを得ず領収書を再発行する際は、以下のポイントに注意して対応するとよいでしょう。ここでは、領収書を再発行する際の注意点をお伝えします。
発行した領収書が残っている場合は回収する
発行時の不備が原因で領収書を再発行する場合は、取引先の手元にある元の領収書を必ず回収してください。元の領収書を回収することで、不正利用などのトラブル防止につながります。
再発行した領収書にも収入印紙を貼る必要がある
領収書の受取金額が5万円を超える場合は、領収書に収入印紙を貼付する必要があります。収入印紙は、印紙税を納付するための証憑です。たとえ再発行した請求書であっても、受取金額が5万円を超える場合は収入印紙を貼付しなければなりません。
なお、電子領収書の場合は、発行・再発行ともに収入印紙の貼付は不要です。
再発行した領収書の収入印紙に関する考え方について、詳細は国税庁のホームページに掲載された質疑応答事例でご確認いただけます。本記事と併せて参考にしてみてください。
出典:国税庁「再発行した受取書」
専用システムで電子化すれば領収書の再発行までラクになる!
ここまで、取引先から領収書の再発行を依頼された際の対応方法や、再発行の注意点について解説しました。
日々の経理業務では、書類の再発行をはじめとしたイレギュラーな対応が発生するケースが少なくありません。例えば、領収書の再発行に応じる場合は、過去の発行履歴を遡って改めて内容を確認したり、取引先へ再度送付したりする手間がかかってしまいます。特に紙で対応すると、書類を物理的に探したり郵送したりと、多くの工数がかかるでしょう。
一方、請求業務に関する書類を電子化しておくと、専用システム上で書類の検索や送付ができるため、定型業務からイレギュラー対応まで経理担当者の負担を軽減できます。
領収書の電子化をご検討中であれば、電子帳票発行システム「楽楽明細」がおすすめです。「楽楽明細」には、経理処理をラクにする魅力がたくさんあります。
魅力① 領収書や請求書などの帳票をなんでも発行できる
システム上であらゆる帳票や書類を簡単に発行できます。領収書のような毎月大量に発行する書類を電子化することで業務効率化を実現できます。紙の領収書を電子化すると、印刷・封入・郵送などの手作業が不要となり、さらには印刷代や郵便料金のコスト削減にもつながります。
魅力② 導入するだけで電子帳簿保存法・インボイス制度への対応が可能
「楽楽明細」は電子帳簿保存法やインボイス制度など最新の法律に対応したシステムです。導入するだけで法的な要件を満たして電子領収書を適切に管理する体制を整備できます。帳票の電子化にともなう法対応に不安を感じている担当者の方もご安心ください。
魅力③ 手厚いサポートで初めてのシステム導入も安心
システムの導入準備から運用開始後まで、一貫して手厚いサポートを提供いたします。専任のサポート担当が支援するため、初めてのシステム導入でもスムーズな運用を実現可能です。システムやパソコン操作に自信がない担当者の方も、どうぞお気軽にご相談ください。
「楽楽明細」について詳しく知りたい経理担当者の方は、以下のページからお気軽にお問い合わせください。導入メリット・機能・料金プランなどを無料の資料でご案内いたします。
【無料】3分でわかる!電子帳票発行システム「楽楽明細」資料請求はこちら>>>
「楽楽明細」
請求書の印刷・封入・発送の作業をゼロに!
面倒な請求書発行の手間を削減します。
オススメの人気記事
- 記事執筆者紹介
- 株式会社ラクス「楽楽明細」コラム編集部
「楽楽明細」のコラムでは請求書や領収書、支払明細書などの各種帳票の発行方法や、経理業務を効率化する方法などについてご紹介します!

注目記事
96%削減できます。※
※ 月の発行件数500件の場合の月間の導入効果(ラクス調べ)


「楽楽クラウド」サービスのご紹介
「楽楽クラウド」サービスのご紹介です。
企業のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ95,000社以上のご契約をいただいています(※2025年3月末現在)。「楽楽明細」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。