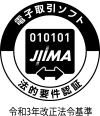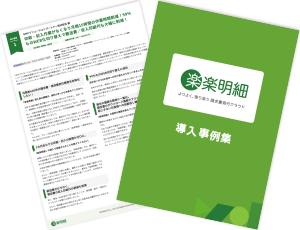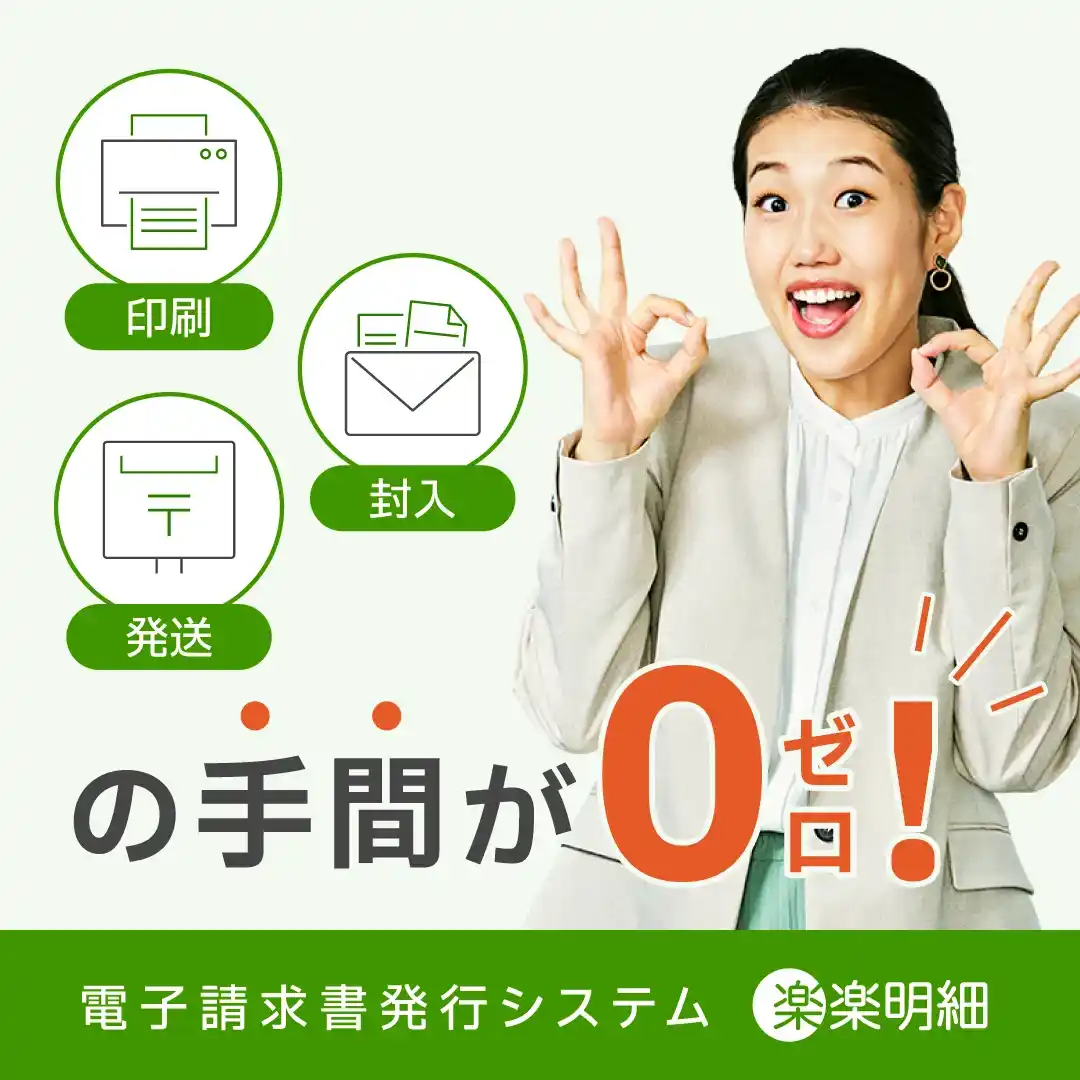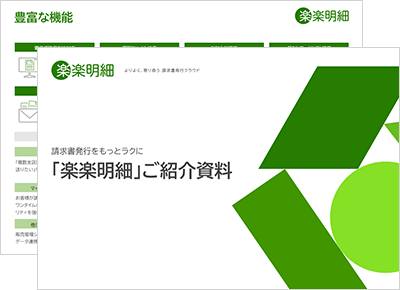領収書を発行する流れとは?作成する理由や発行時のポイント、注意点
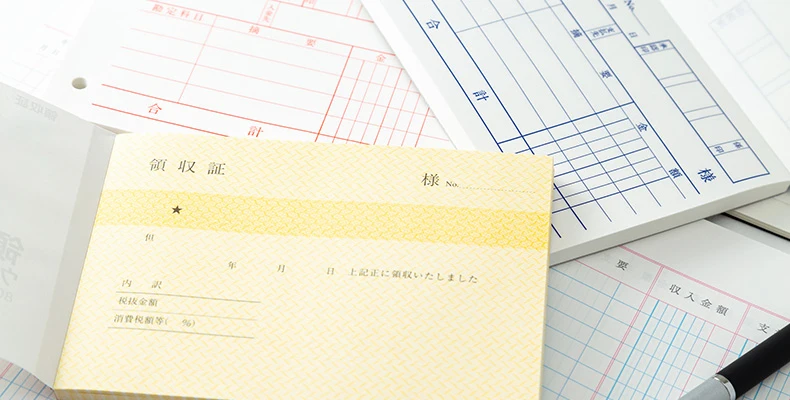
経理業務の中でも領収書(領収証)には、企業間の金銭の支払いを証明する重要な役割があります。企業によっては発行枚数が非常に多くなるため、業務効率を見直し、領収書発行を正確かつスムーズに進められるオペレーションを構築することが大切です。
この記事では、領収書を発行する流れや注意点などの基礎知識を解説します。また、紙での領収書発行にかかる時間と手間でお悩みの経理担当者の方へ向けて、専用システムを活用した業務効率化についてもご紹介します。経理業務に課題を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。

領収書を発行する理由
領収書とは、商品・サービスに対して対価を支払ったことを証明する証憑書類です。金銭の流れを明確にするとともに、トラブルや不正を防ぐ目的で発行します。
はじめに、領収書を発行する理由について詳しく解説していきます。
二重請求・二重支払いを防ぐため
領収書を発行すると、買い手側・売り手側ともに取引の完了を確認できます。金銭授受が確実に証明され、二重請求・二重支払いなどの支払いに関するトラブルの防止につながります。
経費精算における不正を防ぐため
領収書は、受領した企業の経費精算において重要な書類です。発行された領収書は、経費として計上できる取引の証拠となるため、公正な経費精算に役立ちます。企業が会社会計・税務運用を正確に行うためにも、領収書が欠かせません。
領収書発行の大まかな流れ
ここでは、企業間取引における領収書発行の流れを発行側の視点で解説します。
原則、買い手側が領収書の発行を求めた場合、売り手側は領収書の発行に応じなければなりません。
その際、領収書は一般的に以下の流れで発行されるため、経理担当者の方は押さえておきましょう。
Step1.取引内容を確認する
取引先から領収書発行を依頼されたら、まずは対象の取引内容を確認して、提供した商品・サービスや取引金額などを把握します。
Step2.領収書に必要な項目を記入する
続いて、領収書に必要事項を記入しましょう。一般的には、以下の基本項目を盛り込みます。
【領収書を発行する際に記載する基本項目】
- 発行日
- 宛名
- 金額
- 内訳(税率ごとの税込金額・消費税額)
- 但し書き
- 発行者情報
参考:G-GOV「消費税法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)」
なお、インボイス制度に対応する場合は、これらに加えて「適格事業者の登録番号」「税抜または税込価額の合計額」「適用税率」などの記載が必要です。併せて確認しておきましょう。
参考:国税庁「インボイス記載事項チェックシート」
Step3. 収入印紙を貼り付ける
紙の領収書の場合は、取引額に応じて収入印紙を貼付します。記載金額に対する印紙税額は以下の通りです。なお、電子領収書の場合、記載金額にかかわらず収入印紙の貼付は不要となります。
【紙の領収書の印紙税額】
| 領収書に記載された金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上~100万円以下 | 200円 |
| 100万円超~200万円以下 | 400円 |
| 200万円超~300万円以下 | 600円 |
| 300万円超~500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 2,000円 |
出典:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」
最終確認を経て領収書を発行し、取引先へ郵送または電子的に書類を送付します。
Step4. 領収書の控えを保管する
発行した領収書の修正や再発行の依頼が来たときに備えて、控えを保管しておきましょう。法人の場合は原則として7年間保管します。なお、インボイス制度に対応した適格請求書を発行する場合、控えの保管が必須となる点に留意しましょう。
出典:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」

領収書を発行する際の注意点
最後に、領収書の発行に関する注意点を解説します。請求業務を正確に進めるために、以下のポイントを押さえておきましょう。
但し書きには具体的な内容を記載する
領収書の「但し書き」とは、何に対して金銭の授受が行われたかを示す項目のことです。その際、「お品代」のような具体性のない書き方では、取引の内容が不明瞭で書類の信頼性が低くなってしまいます。発行側は「書籍代」「飲食代」のような形で、誰が見ても明確に用途がわかるよう具体的に記載しましょう。
金額の改ざんを防ぐ対策を講じる
紙の領収書を発行する場合は、金額の改ざんを防ぐために、数字の前後に「¥」「―」などの記号を記載する対策が必要です。また、鉛筆や摩擦で消えるインクのボールペンは改ざんのリスクがあるため、書類を手書きする際は使用を避けてください。
領収書は原則再発行できないことを伝える
領収書の再発行は、不正に利用されるリスクが存在するため基本的に避けるのが望ましいです。取引先には、原則として紛失や破損が発生しても再発行できない旨をアナウンスして、事前に断りを入れておくようおすすめします。
領収書の再発行について、詳しくは以下の関連記事で解説しています。本記事と併せて、発行方法や注意点をご確認ください。
領収書は再発行してもよい?依頼された際の対応方法や再発行の注意点
領収書を発行した場合はレシートを回収する
店舗のレジスターなどで領収書を発行する場合、レシートは店舗側が回収するのが一般的です。回収することで、トラブルや不正を防ぐ目的があります。
領収書とレシートはどちらも支払いの証明書類ですが、両方が存在すると同じ支出を二重に計上してしまうリスクがあります。レシートと領収書の両方を顧客に提供しないよう、管理を徹底しましょう。
領収書が発行されないケースも存在する
「公共交通機関の運賃」や「自動販売機での購入」のように、一般的に売り手側が領収書を発行しないケースもあります。これらの経費は、領収書の代わりに出金伝票(=取引を記録する書類)で経費精算が可能なため、必ずしも領収書を発行する必要はありません。
領収書発行を効率化するなら専用システムの活用がおすすめ!
ここまで、領収書を発行する流れや注意点などの基礎知識を解説しました。領収書発行業務は専用システムを活用すると効率化できます。電子データで発行すれば、印刷・押印・三つ折り・封入・郵送といった手作業が不要になり、経理担当者の業務負担を軽減できるのが魅力です。
領収書を電子発行するには?メリットやデータ保存の注意点について
ただ、近年は電子帳簿保存法やインボイス制度などの法改正にともない、どのように電子化を進めればよいのか迷っている担当者の方もいるでしょう。そんなときは、法的な要件を満たしたシステムの導入をおすすめします。領収書発行を電子化するなら、最新の法要件を満たした電子帳票発行システム「楽楽明細」がおすすめです。
「楽楽明細」には、初めての電子化でも安心できるこんな魅力があります。
魅力① 導入するだけで電子帳簿保存法やインボイス制度に対応
「楽楽明細」は電子帳簿保存法やインボイス制度などの最新の法要件に対応したシステムです。ただシステムを導入して適切に運用するだけで、領収書の電子化に必要な要件を満たせます。社内で詳細なルールを把握していなくても、ラクに制度対応を実現できます。
魅力② 簡単な操作で領収書を発行できる
システムが苦手な方でも簡単に使える、わかりやすい画面設計が魅力となっています。帳票発行に特化したシンプルな機能なので入力や操作が簡単で、テンプレートを使ってスムーズに領収書を作成可能です。また、現在お使いの紙の領収書と同じデザインを再現できます。
魅力③ 初めての電子化にも安心のサポート体制
導入前後のサポート体制がしっかりと整備されているので、初めての電子化でも安心です。専任のサポート担当が、導入準備から運用開始後まで手厚く支援し、スムーズな移行を実現します。システム導入に不安がある担当者の方も、どうぞお気軽にご相談ください。
クラウド型電子帳票発行システム「楽楽明細」のサービスについて、詳しくは無料の資料でご紹介しています。機能や導入メリットなどの詳細は、ぜひこちらをご覧ください。
【無料】3分でわかる!電子帳票発行システム「楽楽明細」資料請求はこちら>>>
「楽楽明細」
請求書の印刷・封入・発送の作業をゼロに!
面倒な請求書発行の手間を削減します。
オススメの人気記事
- 記事執筆者紹介
- 株式会社ラクス「楽楽明細」コラム編集部
「楽楽明細」のコラムでは請求書や領収書、支払明細書などの各種帳票の発行方法や、経理業務を効率化する方法などについてご紹介します!

注目記事
96%削減できます。※
※ 月の発行件数500件の場合の月間の導入効果(ラクス調べ)


「楽楽クラウド」サービスのご紹介
「楽楽クラウド」サービスのご紹介です。
企業のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ95,000社以上のご契約をいただいています(※2025年3月末現在)。「楽楽明細」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。