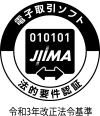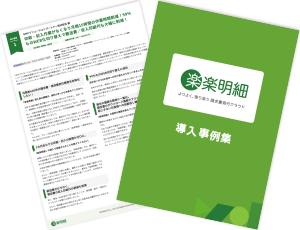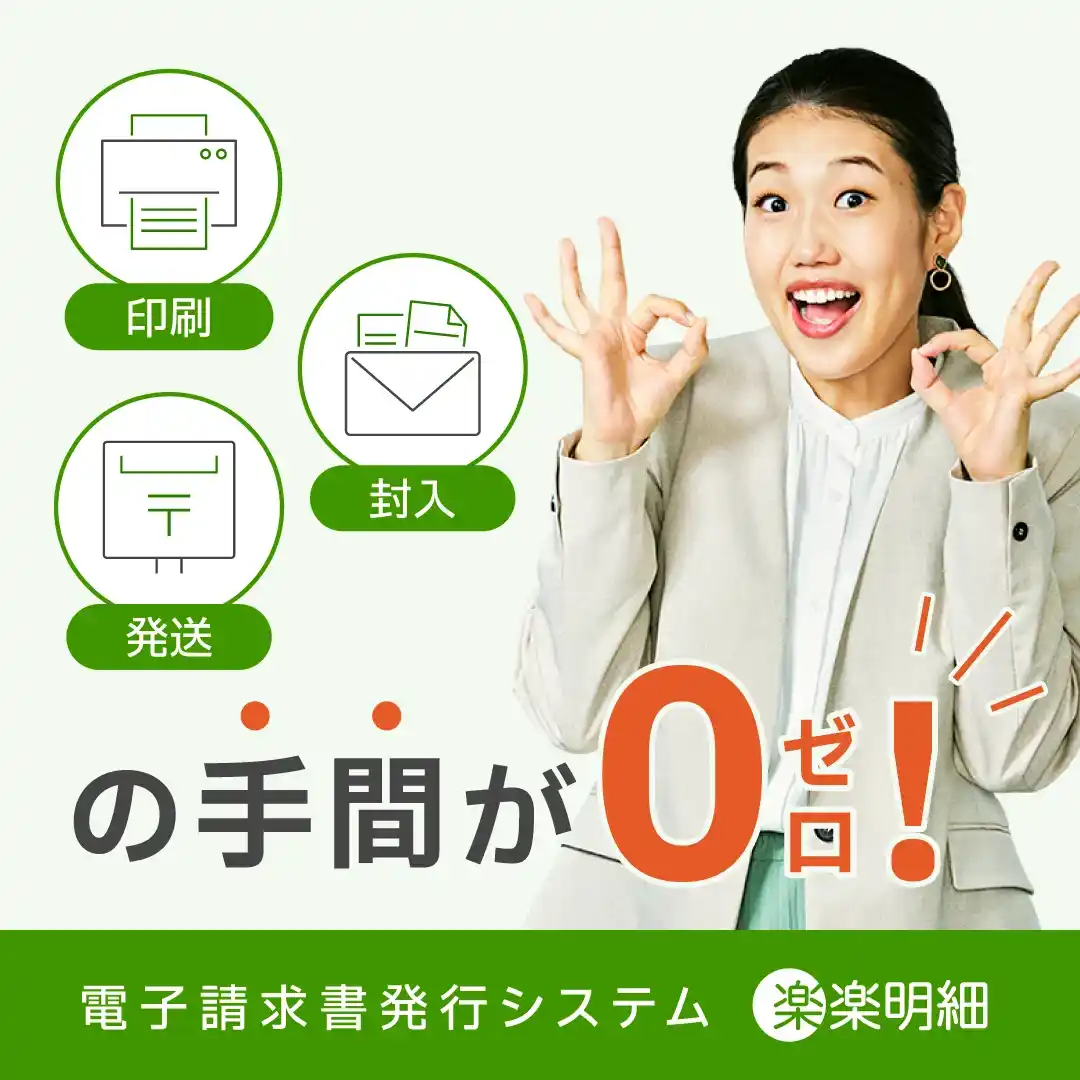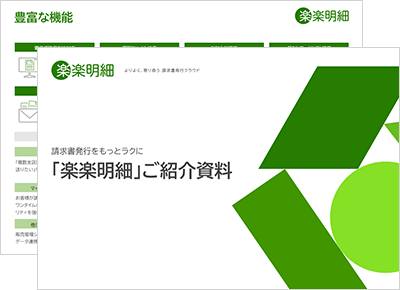納品書に印鑑や角印は必要?

- 納品書に印鑑や角印は必要?
- 納品書のFAX送付の注意点
- 納品書のメールへの添付の注意点とメール文例
- 納品書の整理方法
- 納品書の折り方
- 納品書の送り方
- 納品書の訂正方法
- 納品書の封筒の書き方
- 納品書の保管・保存期間
納品書に印鑑や角印は必要?
納品書に印鑑を押すことは法律上定められておらず、納品書に印鑑や角印が押印されていなくても問題はありません。しかし、日本では「確認」や「認証」といった意味合いから書類に印鑑を押す習慣があり、納品書も例外ではありません。納品書に印鑑を押す場合はどのような印鑑が適応されるのか、印鑑の種類と共にご紹介しましょう。
実印
法人・個人を問わず印鑑登録を行った印鑑を実印と呼び、法人の場合には代表印とも呼ばれています。法人印鑑登録する場合の印鑑の形に規定はありませんが、丸形の印鑑を活用することが主流です。1企業につき1本のみ印鑑登録ができ、重要な契約時などに適応する印鑑となります。
認印
印鑑登録された印鑑以外のすべての印鑑は、認印に分類されます。公的な書類の申請や宅配便や郵便書留など、「確認」や「認証」といった印が必要時に活用される印鑑です。
角印
正方形の印鑑を角印と呼び、法人用の認印として証憑書類に分類される納品書や見積書、請求書といった文書に活用される印鑑です。納品書に印鑑を押す規定はありませんが、企業から発行された公式な文書である証や改ざん防止の観点からも、納品書に印鑑が押すことが主流となっています。
銀行印
銀行口座開設時に登録した印鑑を指します。認印との兼用も可能ではありますが、万が一紛失してしまった際のリスクが2倍になるため、認印と銀行印の各1本ずつ用意することが望ましいでしょう。
シャチハタ印
印鑑内にインクが内蔵されているために朱肉を必要とせず、その利便性からも多くのシーンで活用されている認印の一つです。しかしシャチハタ印はゴム製であるため、力加減で印影が変化してしまうデメリットがあります。こうした背景からも公的な書類には適応されず、宅配便や書留の受取時などに適応する印鑑と広く認識されています。
電子印
「e-文書法」で証憑書類の電子化が一部認められ、電子印鑑も活用されるようになりました。ただ印影をデータ化しただけではなく、電子印鑑の持ち主の情報や押印した日時などの情報を取り込むことが可能であり、改ざん防止します。
【無料】3分でわかる!帳票電子発行ソフト「楽楽明細」資料請求はこちら>>>
「楽楽明細」
請求書の印刷・封入・発送の作業をゼロに!
面倒な請求書発行の手間を削減します。
注目記事
96%削減できます。※
※ 月の発行件数500件の場合の月間の導入効果(ラクス調べ)


「楽楽クラウド」サービスのご紹介
「楽楽クラウド」サービスのご紹介です。
企業のあらゆるお悩みを解決できるシステム・サービスをご用意しています。

おかげ様でラクスグループのサービスは、のべ95,000社以上のご契約をいただいています(※2025年3月末現在)。「楽楽明細」は、株式会社ラクスの登録商標です。
本WEBサイト内において、アクセス状況などの統計情報を取得する目的、広告効果測定の目的で、当社もしくは第三者によるクッキーを使用することがあります。なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWEBブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。